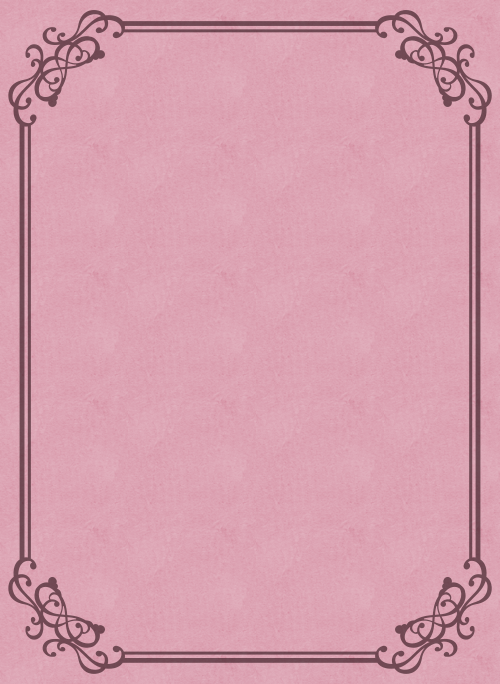けれども一向に私を撫でる手をやめない。それどころか強くなってる気がする。
「もう、達久のばかっ、やめてって言ってるのにどうして撫で回すのっ」
「あははっ」
あまりに屈託無く彼が笑うものだから、なんだかこっちまで笑いたくなってしまう。
お返しとばかりに私も達久の頭に手を伸ばす。
けれど届かなくて、その事実に少しだけ絶望したあと、仕方なくほっぺたをつねってやる。
笑いながらつねられて崩れた顔は、まるで二年前の達久みたいだ。
私より2歳年下の、可愛い従兄弟に戻ったみたい。
久しぶりの幼い笑顔が、私の心をしゅわしゅわと解いていく。
「もう……いやだ」
きっと祭りの喧騒で彼にこの呟きは届かない。
聞こえなくてよかった。
愛しさの滲んだ、いやだ、なんて彼への親愛以外の何者でも無い。
どうせ声が聞こえないなら、私の顔も彼から見えなくなればいいのに。
こんな緩んだ顔なんか本当は見られたくなんかない。