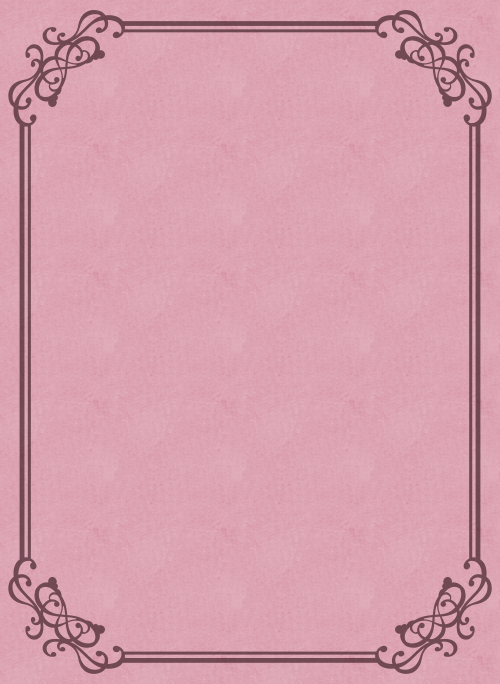「……恋って難しいんだね」
佐野は悠里を好きで。
悠里は達久を好きで。
そして達久にも、好きな子がいるという。
みんな、誰かに一生懸命になっている。
それが彼らを眩しくさせている。いいな、と思った。
「美琴は好きなやつとかいないのか?」
いちご飴を食べ終えたらしい佐野が、ぺろりと舌を舐めながら聞いてくる。
私はというと、齧って半分になったいちご飴の赤が、とろりと宵宮の光を吸うのを見つめながら、好きとはどういう感情なのだろうと思いを馳せた。
「……いたことないんだ、好きな人とか」
高校生にもなって変だよねと、くしゃりと笑う。
残りの飴を口に入れると、ガリガリと飴の固さに混じって、熟しきった苺がどろりと舌を這う。
酸っぱさの抜けた苺は、ジャムのように甘くて、じりじりと痺れるようだった。
恋なんて、したことない。
恋はきっと怖い。ひとを、変えてしまうから。母も変わってしまったから。
私がこんな歳になってから恋したって、それは酸っぱい初恋になんてならない気がした。
どろりと胸を伝っていく苺みたいに、私のそれはきっと甘い毒にたっぷりと浸った、どうにもならない恋になる気がした。
……まるでそうなるのが母からの呪いであるように。
「……いたことないんじゃなくて、気付いてないだけだったりして」
「え?」
「案外、ずっと好きな人がいるのに、それが恋って気づいてないだけかもな、美琴は」
佐野はそういってにやっと笑った。
なんだか佐野のくせにとても生意気な気がして、ばーか、と舌を出した。