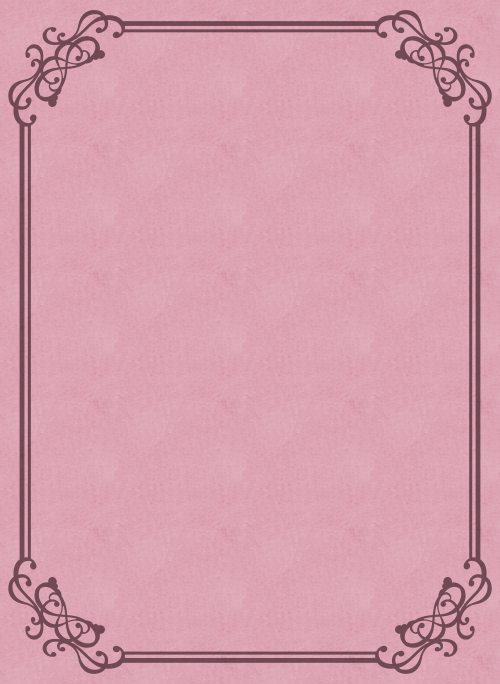へえ、と相槌を打ちながら、前を歩く悠里を見る。
淡い白と紫が滲んだ雲のように見える浴衣は、達久の紺のものともよく合っていた。ともすれば、あえて色味を合わせた私よりも。
アップにした髪に、きらりと光を弾く簪を挿して、隣にいる達久を頬を染めて見つめている。
素直に、可愛いなと思った。
好きなひとが隣にいて、それが幸せだと、彼女の全てが物語っている。
だからこそなおさら、佐野が可哀想だった。よりによって、悠里と悠里が好きな男の子とお祭りに来ることになるなんて、佐野も災難だ。
「なんで、いいなって思い始めたの?」
そう尋ねると、佐野は少しだけ笑った。恥ずかしそうにはにかむ佐野もまた、恋をしている顔だった。
「あいつ、考えてることなんでも顔に出るんだよ。それが、眩しいんだ」
「……ああ、それは分かるかも。憎めないんだよね、考えてることが分かるから」
「そうなんだよなー、
俺がつまんない冗談言ったら露骨につまんなそうにするし、俺が試合で点決めたら本気で嬉しそうに手を叩くんだ。
マネの先輩に怒られたら全力で泣くし、でも、一回怒られたら頑張って直そうとする」
そういうとこに惹かれたんだよなあ、と苦笑いした。
「最近彼氏と別れたって聞いてさ。
そんなときに祭りに誘われたから、舞い上がっちゃったんだよなあ、俺」
ぽりぽりと後ろ首を掻きながら、困ったように佐野は笑った。その顔がなんだかとても切なくて、こちらまで苦しくなった。