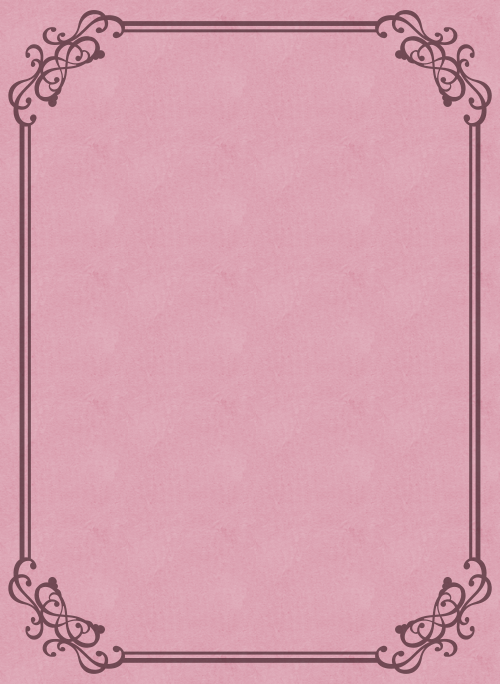「ああ、そうそう、今日は晴子にこれを預かって欲しくて持ってきたんだ」
思い出したように、父は数冊の分厚いアルバムをトートバッグから取り出した。
随分年季の入ったそれは、私も久しぶりに見るものだった。
「引っ越すときにうちから持ってきたんだけど、結構嵩張るんだよなあ。大事にとっておきたいんだけど、一人暮らしだとなかなか手狭でさ。達久くんの写真もかなりの数入ってるし、ついでにこの家で持っててくれないかなあ」
「まったくもう、ここぞとばかりに荷物押し付けるんだから。仕方ないわねえ」
交わされる会話を聞きながら、そっとアルバムをめくる。開くときに、きしきしと厚いアルバム特有の抵抗を感じる。
それは私が生まれた時からの記録だった。
捲っていくと、当然だけど若いときの母の姿が写っていて、なんとも言えない気分になる。
もしかしたら、母の写真を手元においておきたくないのかもしれない。
父を見ながらそんな邪推をしてしまう。
……でももう8年経ってるんだよ、と言い訳のように心の中で呟いてみたけれど、私も乗り越えられているかと言われたら微妙なところだ。
「懐かしいわねえ」
大きくなっていくにつれて、達久と私の写真が増えていく。
家も歳も近いこともあって昔から仲がよかった。
一緒に海に行った夏の写真、おもちゃを取り合って喧嘩している写真、誕生日の写真……。
当たり前だけれど、一緒にいた時間の方が話していないここ2年間なんかよりもずっとずっと長いんだと実感する。