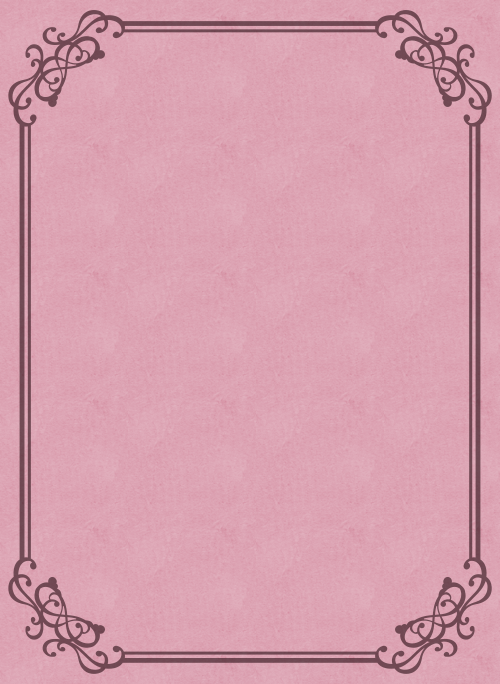昼休み、売店でサンドイッチを買って頼子と教室に戻ってくると、なんとなくうちの教室の前の廊下がざわついている気がする。
「なんだろ」
即座に反応したのは頼子で、私も首をかしげる。
なんとなく浮き立った雰囲気を遠巻きに見ながら教室に入ると、女子数人が私たちのところに集まってきた。
「美琴、あれ、あんたの彼氏なんだって!?」
「……ちょっと待てなんの話だ」
「だからっ、あのめっちゃかっこいい中学生!今廊下にいるじゃんっ」
鼻息を荒くして彼女たちは一点を指差した。
中学生、という単語に嫌な予感がする。
「美琴まじか、あんた中学生が好きなんか。やるじゃんぴゅーぴゅー」
「まって頼子分かってるくせに悪ノリしないの、そしてその下手くそな口笛やめなさい」
沸き立つ彼女たちに、とにかく彼氏じゃないと声高に宣言して急いで廊下に出る。
さっきなんとなく違和感を感じた廊下の空気の正体、それは紛れもなく我が従兄弟のものであった。
「……遅い、美琴」
「美琴じゃなくてミコ姉でしょ、呼び捨てなんか許してないんだからねこのニセ彼氏」
「いい嫌がらせになったでしょ?」
くつくつと喉の奥で笑って、廊下の壁に背を預けていた達久はこちらに近づいてくる。
中等部の緑色のネクタイを着崩しもせずきっちり着こなして、眼鏡の奥で緩く目を細められると、端正な顔立ちのおかげもあってなるほどそこらへんの男子よりも品があるから目が吸い寄せられる。
「……ほんと、いい嫌がらせを思いついたもんだね、達久」