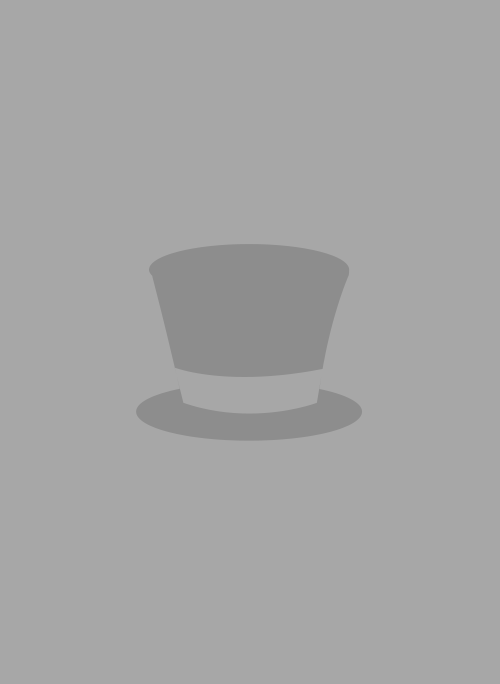私が泣きじゃくっているあいだ、お兄ちゃんはずっと私の手を握ってくれていた。
「うっ...ひぐっ...」
「大丈夫か?ほら、お茶飲んで。ストローささってるから。」
嗚咽を漏らす私の手に、お兄ちゃんがコップを持たせてくれた。
手の感覚だけでストローを探し、なんとか口元まで持っていき、お茶を吸った。冷たい。
目が見えないことにより、平衡感覚が随分と失われてしまったので、コップを真っ直ぐ保つのもすごく体力を使う。
今までは目が見えるなんて当たり前だと思ってたけど、いざ見えなくなると、どれほど大変かがよくわかった。
私はコップをお兄ちゃんに返し、またゆっくりと横になった。
「ねえ、お兄ちゃん」
「何だ、颯?」
お茶を飲んでも、声の震えは治まらない。
「この目はさ、もう一生治んないのかな?」
声に出してみると、やっぱり苦しくなって、止まったはずの涙がまた流れ落ちた。
「...」
お兄ちゃんは何も言わない。
きっと、答えられないんだろうな。
「そりゃ、そうだよね。あたしが夜にあんな所に行くから悪いんだもんね。自業自得だよね。」
私の喉からは、カラカラと乾いた笑いが出た。
「そん...」
バァン!
何か言いかけたお兄ちゃんの言葉を遮るように、突然病室のドアが勢いよく開いた。
私は音のしたほうを振り返った。相変わらず何も見えないけど。
途端、怒声が響き渡る。
「宙っ!颯っ!」
えっ?えっ?
何?誰?
私のその疑問に、お兄ちゃんが答えてくれた。
「あ、母さん!」
うそ、お母さん?!
意外と覚えてないもんなんだ、人の声って。
実の母親の声さえ分かんないなんて。
てか絶対怒ってんじゃん...
カツカツとハイヒールの音が迫ってくる。
ひゅ、と風を切る小さな音が耳元でなった。
と同時に、左の頬に鈍い衝撃が走る。
「っ...」
お母さんに平手打ちされたのは何年ぶりだろうか。
不覚にも、また涙が落ちた。
「バカっ!何でいつもお母さんの言う事を聞かずに夜遊びするの?!だからこんなことになるんでしょう?!前まではすごくいい子だったのに...。何が颯をこうさせたの...?もう心配かけないで...よ...」
最後の方はほとんど聞き取れなかった。
私はどうにもやり切れなくなり、布団に潜り込んだ。
「うっ...ひぐっ...」
「大丈夫か?ほら、お茶飲んで。ストローささってるから。」
嗚咽を漏らす私の手に、お兄ちゃんがコップを持たせてくれた。
手の感覚だけでストローを探し、なんとか口元まで持っていき、お茶を吸った。冷たい。
目が見えないことにより、平衡感覚が随分と失われてしまったので、コップを真っ直ぐ保つのもすごく体力を使う。
今までは目が見えるなんて当たり前だと思ってたけど、いざ見えなくなると、どれほど大変かがよくわかった。
私はコップをお兄ちゃんに返し、またゆっくりと横になった。
「ねえ、お兄ちゃん」
「何だ、颯?」
お茶を飲んでも、声の震えは治まらない。
「この目はさ、もう一生治んないのかな?」
声に出してみると、やっぱり苦しくなって、止まったはずの涙がまた流れ落ちた。
「...」
お兄ちゃんは何も言わない。
きっと、答えられないんだろうな。
「そりゃ、そうだよね。あたしが夜にあんな所に行くから悪いんだもんね。自業自得だよね。」
私の喉からは、カラカラと乾いた笑いが出た。
「そん...」
バァン!
何か言いかけたお兄ちゃんの言葉を遮るように、突然病室のドアが勢いよく開いた。
私は音のしたほうを振り返った。相変わらず何も見えないけど。
途端、怒声が響き渡る。
「宙っ!颯っ!」
えっ?えっ?
何?誰?
私のその疑問に、お兄ちゃんが答えてくれた。
「あ、母さん!」
うそ、お母さん?!
意外と覚えてないもんなんだ、人の声って。
実の母親の声さえ分かんないなんて。
てか絶対怒ってんじゃん...
カツカツとハイヒールの音が迫ってくる。
ひゅ、と風を切る小さな音が耳元でなった。
と同時に、左の頬に鈍い衝撃が走る。
「っ...」
お母さんに平手打ちされたのは何年ぶりだろうか。
不覚にも、また涙が落ちた。
「バカっ!何でいつもお母さんの言う事を聞かずに夜遊びするの?!だからこんなことになるんでしょう?!前まではすごくいい子だったのに...。何が颯をこうさせたの...?もう心配かけないで...よ...」
最後の方はほとんど聞き取れなかった。
私はどうにもやり切れなくなり、布団に潜り込んだ。