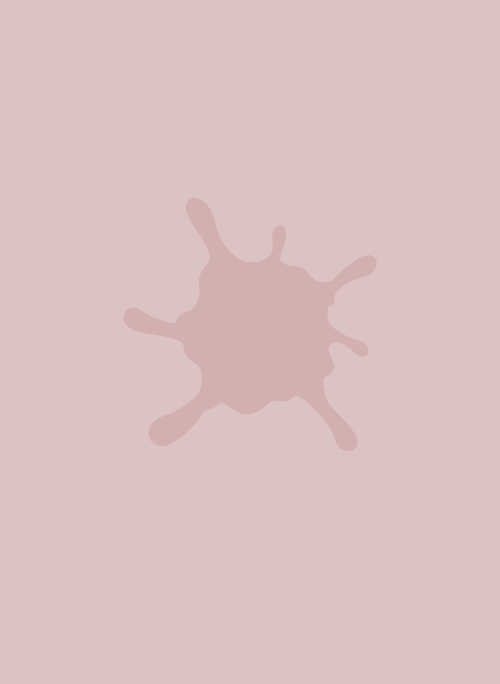「もし、私が先輩の紅茶に薬を入れていたらどうします?」
相の変わらない放課後の蔵書室。ひな乃は取り留めのないことのように、ごく自然にそう言った。俺は驚きとは言えない、しかし何だか胸騒ぎのようなものを感じてしまった。
ひな乃が、俺の紅茶に薬を。恐らく、ひな乃の言う薬というのは、悪い薬__例えば睡眠薬とか、そんな類のものだろう。ひな乃が実際にそうしているとは考えにくいが、表情を少しも変えずに冷徹な眼差しで温かい淹れたての紅茶に、粉薬を注ぎ込む様子が安易に想像できてしまうのも問題だった。
「どうするって…その、薬にもよるだろう」
「じゃあ仮に、私が紅茶に薬を入れていたとして、」
ひな乃は一瞬だけ、躊躇うように言葉を止めた。
「その薬がもしも、飲んではいけないものだったら?」
「それって、違法…のやつとかのことか?」
ひな乃は肯定する代わりに薄い笑みを浮かべた。
どうして、そんなことを聞くのだろうか。俺の紅茶にそのような薬を混入させていたら__俺は怖くて思わず身震いしてしまった。しかしひな乃の笑みは軽いものであり、真剣に聞いている様子ではないように感じられる。
「そ、そんなの、そもそもあり得ない。
それより、俺が今日ここに来た理由なんだけど、分かってるよな」
「そうですよね。私は、先輩の紅茶に薬など、異物は一切入れていません。断言するから、安心してください」
ひな乃の真っ直ぐな眼差しに、これが真実であることを確信する。少し怖かったが、ひな乃は嘘を言っていないだろう。そう判断できる明確な理由はないが、恐らく、この蔵書室に通うようになってからひな乃に対する信頼が生まれていたのだろう。
そして俺が聞きたかったのは他でもなく、2日前の出来事だった。ひな乃に氏家邸へ連れて行かれ、そして目の当たりにした、暗い地下室で起こっていたあの出来事。
土日を挟んでしまったのですぐに聞き出せなかったが、質問したいことは山ほどある。俺は、先程放課後になってこの蔵書室に入る前、一年生のフロアにいる浅井さんに会いに行った。2日前に別れたときは落ち込んでいたが、それなりに回復している様子だった。心に負った傷はどうなのか分からないが。
「分かっています。先輩は、私と関わってしまい、«死神»と関係を持ってしまった。だから、ほんとうのことを言わなければならない…」
「その死神っていうのもなんなんだ。いい加減、教えてくれ。相模も同じことを俺に言ったけど、ひな乃の言う死神とはまた違う感じだった」
「お互いにとって自分を壊して破滅させる存在です。それでもなお、一緒にいなければならない共依存のようなもの」
ずっと秘密にしていたことを曝け出すように、ひな乃は一度口を噤み、そしてもう一度赤い唇を開いた。