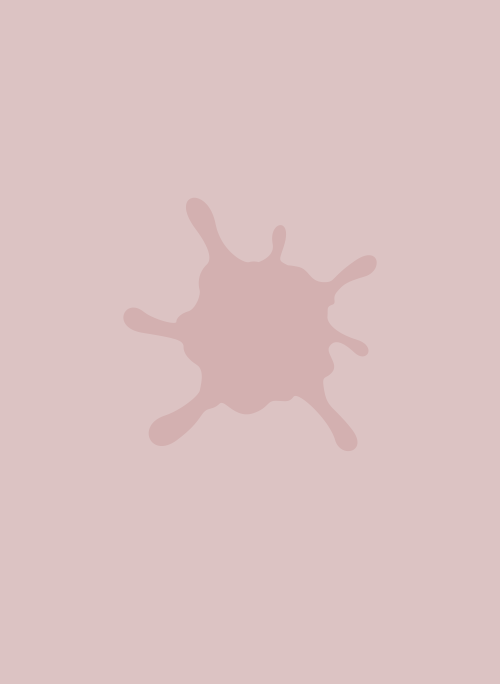「あの、裕貴さん、その紅茶どうですか」
裕貴さんの飲む紅茶は、俺が、父さんに頼まれ選出したものである。と、言ってもイギリスから取り寄せた、アールグレイのストレートだが。
「上品な味わいだよねぇ。僕の家、あんまり紅茶飲む機会ないから、茶会、いつも楽しみにしてるよ」
「あ、ありがとうございます」
そうか、俺は参加してないけど、裕貴さんは駿河主催の茶会に来ていたんだ。
他にも、氏家ほどの資産がある大企業は、様々なパーティに呼ばれるのだろう。
「良かったです」
「ああ、ところで」
「はい?」
「清條院に、僕の従妹が__」
いとこ?
その時、裕貴さんが舞台の方に目をやった。
氏家の社長、つまりは裕貴さんの父が、こちら、裕貴さんに目配せしている。
それが、どうやらこちらへ来いの合図だったようで、彼は失礼、とティカップを片手に立ち上がった。
「さっきの話は、またあとでね」
ウィンクをして、去って行くのであった。
それから、父さんの挨拶により、新車が発表された。シルクのカバーを剥がし、照明に輝く車体は、場を大いに盛り上げた。
茶会の目的は、達成できたと思う。
プロジェクターで写した映像で車体について説明していく。それも、米国のあの会社を思わせるような宣伝で、好評を博していた。
その後は茶会を楽しみましょう、という流れになり、俺は一度会場を出た。お手洗いに行くためだ。
用を済まし、ハンカチで手を拭きながら、臙脂色の絢爛さ漂う柄のカーペットの敷かれた廊下を歩く。
すると__。
廊下の突き当りに、俺へ身体を向け、立ち止まる男がいた。俺よりも、身体が一回りほど小さく、中学生くらいかと思われる。
しかし、この茶会には来ていないはずだ。
けれど、何故会場に繋がる廊下を歩いている?
顔は良く分からなかったが、なんとなく不気味な雰囲気を感じる。禍々しい、負のオーラというか、深淵のような全身から溢れる根暗さを。
会場に戻るには、この突き当りを右折せねばならない。
何となく、怖いというより、彼に違和感を感じる。
何かが、引っ掛かる。
しかし相手の服装はどこかの制服で、正装と呼べる着こなしだった。会場に来ている誰かの子息なのだろうか。
そのまま彼を横切る。
そして、いつかのあの時を思わせる__あの薫りがふわりと鼻腔を突いた。
勘違いかもしれない、うちの茶会で、紅茶の匂いが混ざり合ってこの薫りを成したのかもしれない。
けど、その薫りはあの__。
俺が振り返った時、彼は俺に背を向け歩き出していた。