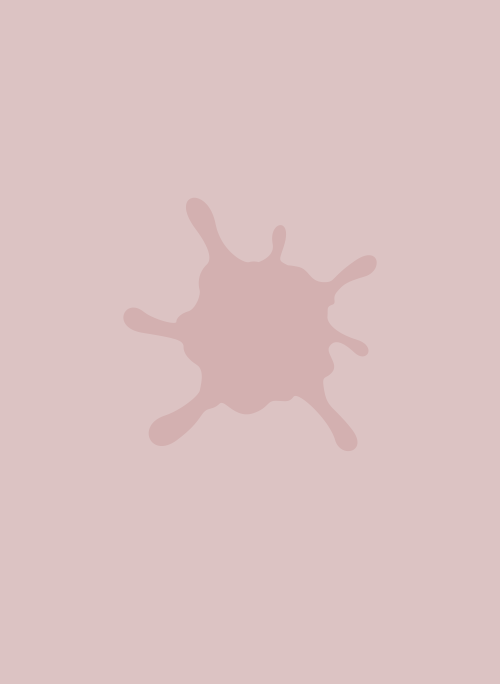こちらからだとひな乃の後ろ姿しか見えないので、どんな表情を浮かべているのか分からない。
だが、凍てつく氷のような目つきが俺の頭を過った。
ひな乃は有無を言わさない、整然たる態度で語り出した。
「私は、駿河先輩に注意をしたのです。ですが、曖昧な言い回しだったので上手く伝わらなかったようで」
ティカップを新聞紙に包み、丁寧に鞄へしまう。
その仕草は至って平然としていて、軽やかで、ひな乃が遠い存在に感じられる。
「«死神»__あの女は、貴方から生気を奪います。«毒牙»を持って、何度でも駿河先輩の元へ訪れるでしょう、怨み殺されるのも、近いでしょう」
__駿河先輩。
ひな乃が俺をそう呼ぶ時は、強く、牽制をする時。
蛇に睨まれたように、金縛りにあったかのように、身体が動かない。
しばらくひな乃がそのような態度を見せることはなかったし、具合悪そうにした時頼ってくれたので、安心し切っていた。
夜空にある星々のように、確かに目に見えるのに手を伸ばそうが絶対に届かない。朝になれば霞んで見えなくなる、幻想のようで。
ひな乃に近付けた、と思ったのはただの思い上がりで、もっと知りたいなどと欲を覚えたのは、恥ずかしい勘違いでしかなくて。
だから、こうして俺を侮蔑する目で見据え、駿河先輩、と俺を呼ぶのだ。
ひな乃は黙りこくった。俺は、茫然とするほかない。
「私のことを、信じてくださるのならば__…」
「…ひな乃?」
「私以外を、見ないで…信じないでください」
漆黒の瞳が哀しげに揺れた。
先程までの凛とした口調が嘘みたいに、弱々しくて、胸が締め付けられる。
ひな乃が弱気な表情でそんな風に言うのは、初めてで、俺の心は、磁石のように惹きつけられていく。
欲しかったモノを、思わぬ形で得た。そんな、違和感のある言葉と表情だった。
「ごめんなさい、今のは忘れてください。嘘、です。先に、帰りますね」
ひな乃は視線を落とした。
瞳を縁取る、黒い柔らかなまつげを揺らす、瞬きにすら集中して魅入る。
今の言葉は、俺に対する、その…独占欲なのだろうか。
それとも、また別の、意味深長なニュアンスで語ったのだろうか。とはいえ、“嘘”と撤回したので意味のない言葉なのかも知れない、。
しかし、俺の心臓の鼓動は鳴り止まない。頭が、パンクしてしまいそうなくらい、パニックに陥っている。
そんな俺をよそに、2本に結われた髪を揺らし、スカートをヒラリと翻して、ソファを横切り、狐色のドアへ吸い込まれていく。
「駿河先輩」
__日曜日、楽しんできてくださいね。
その口調は、もう、普段のひな乃のものであった。