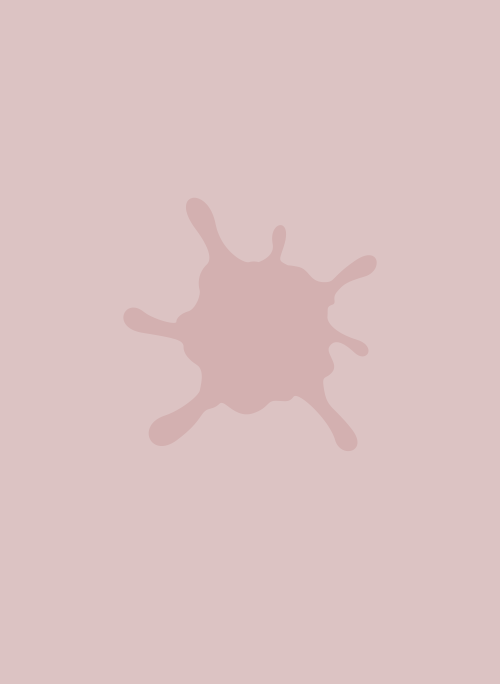「先輩、次の日曜日お暇ですか」
__冬至を目前とし、日没時間が早まったため、蔵書室のカーテンの隙間からはすっかり闇夜に覆われた空が見える。
微かに月の光が差し込み、明石 ひな乃を艶々と、神々しい存在のように照らす。
俺は、ひな乃の出してくれた紅茶を味わい、飲み込んだ。
温かい液体が身体に染み渡っていく感覚は、クセになる。
「次の……って、明後日?」
…明後日の日曜は、あいにく駿河主催の茶会である。
「前回、お断りしてしまったので、…埋め合わせって言ったらなんですけど」
「あぁ…そうか。折角なのにすまないけど__その日は家の用で」
俺の目を真っ直ぐ見て、顔色ひとつ変えることなく彼女はそうですか、と冷淡に告げた。
別段、動揺ことも驚くこともなく、もちろん、残念がる様子もなかった。
「やっぱり、お忙しいのですね」
「ん?いや、前にも行った通り、ほんとうに忙しくないから」
俺は、それよりも先日俺が断られた誘いを、ひな乃が気にしていたことに驚く。
あの、“またの機会に”は社交辞令で、俺と学校外で会うのは拒否されたということだと認識していたから。
ああ、こんな誘いがあると分かっていれば、茶会に行かないと言っていたのに。
いや、駄目だろう、私情で大事なパーティの参加を断るのは。
「ところで、先輩__」
ひな乃がティカップを割れ物を扱う丁重な動作でテーブルに置いた。半分に減った中身は、天井の蛍光灯の灯りをキラキラと反射させている。
そして、ひな乃は自分の真後ろの方角__月光が差し込む窓の方__へ身を傾け、半開きのカーテンの覆う窓を指さした。
「__綺麗、ですね」
「…?」
夕闇に浮かぶ、金色の三日月__。
それを讃えるように、無数にまたたく、細かな塵のような星々。
ここ、清條院は都心から外れた郊外にあるが、少し田舎なだけで、ここまで星が見えるとは。
俺は、初めて清條院学園からの夜空に関心を向けた。
黙りこくって、星空を眺める。
寡黙に空を見つめる俺の心中を、どう察したのか、
「先輩、下げますね」
俺の、飲み終えて空のティカップと、自身の半分ほど残ったままの紅茶を盆に乗せ、片付け始めた。
腕を捲るやいなや、せっせとバケツに含んだ水と洗剤で泡立てていく。
その背中は、どこか、郷愁を漂わせていて、胸が締め付けられる。
また、俺は無意識にひな乃の機嫌を損ね、傷つけてしまったのだろうか。
そんな疑念を持ち始めた。
「この前私が言ったこと覚えてますか」
「何?」
「«死神»のことです」