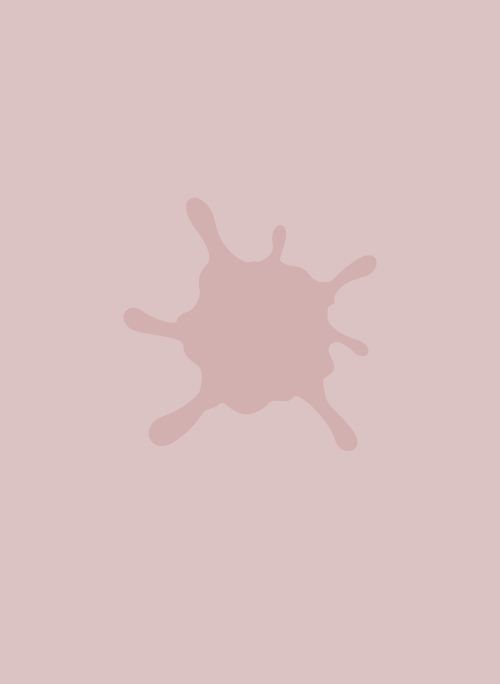やはり会社を担う第一人者として、身なりは整っているが、仕事に一段落着いたとしてもせわしい日々を送っているはずだ。
茶会だって、帝京ホテルの装飾や食事の用意は手間のかかるもののだろう。
「氏家さんのところの、祐貴さんも来られるそうよ」
母さんが、洗い物を終えたのか、再び父さんの隣に腰掛けた。
祐貴さんというのは氏家物流の一人息子。
俺より4つ年上で、昨年成人を迎え、本格的に氏家を継ぐべく、大学生活と修行を両立させている、すごい人。
勤勉性や社交性が買われていて、その業界では有名だ。勿論、血の滲むような努力の上で手に入れた功績であり、自慢げにそれを ひけらかすことがないところも謙虚で、御曹司の鑑である。
氏家は駿河の車の輸出に深く携わっていて、元を辿ると同じ時代に設立した会社であるらしい。
そんな歴史的背景があるので、氏家と駿河は深い親交があり、プライベートでも仲良くしている。
「あぁ、うちの工場の方に見学をしに来たんだが、その時に詩暮に久し振りに会いたいと言っていたよ」
「俺に?」
「最後に会ってから、1年以上経ったんじゃぁないの?」
母さんが薬指にシルバーの指輪をはめた左手を頬に当てる。
同様に、父さんも指輪をはめていて、ふたりが外しているのを見たことがない。それよりも、喧嘩すらしないふたりだ。
これからも夫婦円満のままで、その証を輝かせて欲しいと思う。
「いや、もっと…2年は会ってないと思う」
俺が中学を卒業した時くらいだっただろうか…大学の帰りか何かに、家に来たのが最後だったと思う。
手土産にバームクーヘンの入った紙袋をぶらさげて、大学生活や、会社の手伝いのことなどを語ってくれた。
幼い頃は、互いの家に、親同伴だが…気軽に行き来する程の仲だった。しかし、祐貴さんは特に最近、せわしく動き回っているようで、会う暇すら中々ない。
俺もやがて、駿河を継ぐ道を邁進することになるのだろう…。
忙中有閑とは言うが、自由な時間は今と比べたら、ほとんどなくなるのだろうな。
「そんなに経ったのねぇ」
「光陰矢のごとしと言うだろう。 めまぐるしい日々を送ると、ほんとうにその通りで、あっという間に時は過ぎるものだ。
詩暮は、今、目の前にあるものを大切にしなさい」
父さんは、ワインで少し酔いが回っていたのか、普段と比べて饒舌になっていた。
だが、それでも荘厳な眼差しは、大切なことを喋ってくれているのが伝わる。
俺は、紅茶に再び口をつけた後、深く頷いた。
その言葉は、将来に多少なりとも不安を持っていた俺にとって、暗澹たる気持ちを安らげるものとなった。