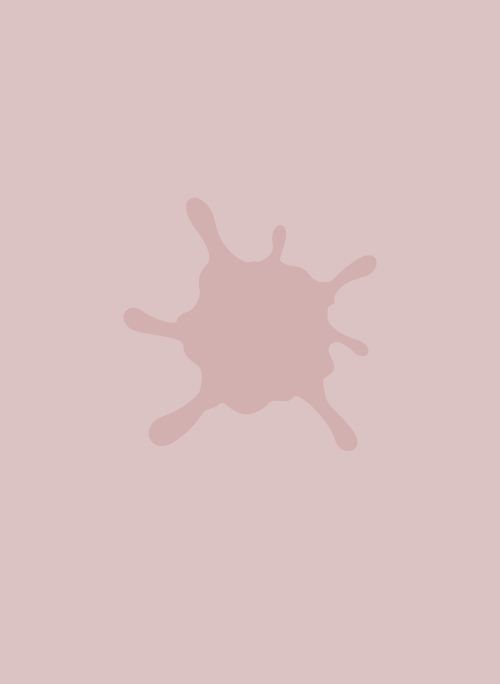そんな風に、もの思いにふけりながら、課題を円滑に進めていると、突如鳴り出したノック音が、思考を妨げた。
ああ、と、部屋の壁掛け時計に目をやると、丁度我が家の夕飯時であった。
部屋を出ると、使用人の和泉が立っていて、ばっちりアイロン掛けのされたスーツに身を包んでいる。
和泉は、もうじき還暦を迎える、駿河家に昔から雇われている執事である。白い髭が、いかにもな雰囲気を漂わせていて、聡明剛気の信頼における人物だ。
「詩暮さん、ご夕食の準備が出来ました。旦那様と奥様が、食堂でお待ちになっておられます」
「ありがとう」
俺が物心つく前は、“詩暮様”と呼んでいたのだが、俺の所望で様付けはやめてもらった。
かと言って詩暮坊ちゃんと呼ばれるのもなんだか性に合わないので、“詩暮さん”だ。
「父さん帰ってるの?」
「はい、お仕事に切りが付いたとのことで、お見えになっています。詩暮さんにお会いできるのを、心待ちにしておられますよ」
「あぁー…」
そういえば父さんは、新開発の車がどうのこうのって、数ヶ月前辺りに言っていた気がする。
多機能を搭載した、新しい試みで、大々的に取り組んでいたらしい。
最近巷でよく聞く、人感センサーとやらに力を入れていて、いくつかの会社の車で試験走行をしたところはニュースにもなっていた。
「それでは、失礼します」
和泉は頭を下げ、食堂とは逆の執務室の方へ戻っていった。
食堂に着くと、豪勢な食事がテーブルに並べられていた。
大皿に乗ったグラタンや、暖かそうなかぼちゃのスープ、色とりどりの野菜などが、ビュッフェのように配置されている。
隣り合った椅子に腰掛ける、父さんと母さん。
目の前にはワインの瓶がある。お祝いごとがあったかのような食卓だ。実際、そうなのかもしれないが。
俺は、ふたりの向かいの椅子を引き、腰掛けた。
「中々、帰れなくてすまなかったな」
同時に、父さんが荘厳そうな雰囲気を醸し、語り出す。
「新車の開発が終わって、合間を見て戻ってきたんだ」
「そうなんだ、お疲れ様」
「おめでたいから、頑張ってご飯作ったのよ」
母さんは自らの髪に触れながら、にこりと笑った。
ショートに整えられたそれは、天井に吊るされた灯りに照らされ、歳の割には艷やかに見える。
今日は、仕事の無い日なのだが、バッチリメイクが施された顔は、サバを読んで二十後半…と言っても平気な程度だ。
旦那が駿河の社長だから、外見に気が抜けないのもあるのだろう。