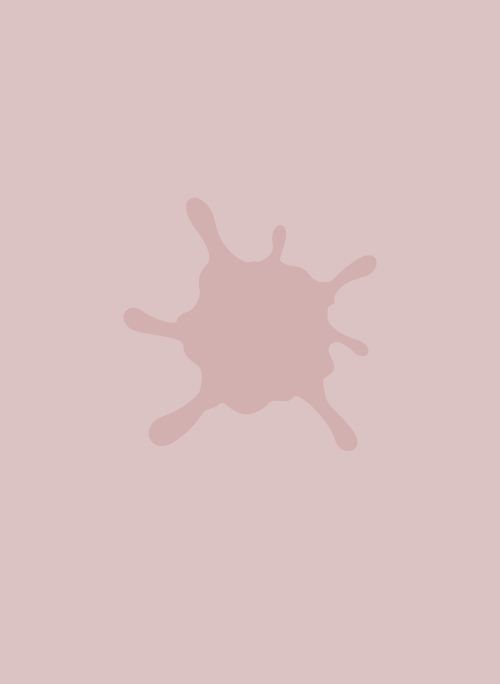やがて、相模が俺を睨む目は和らいできて、俺に縋りついていた身体を離した時には、すっかり元の表情の乏しい顔に戻ってしまった。
急激な変貌の繰り返しに、あっけらかんとする俺である。
「ごめんなさい、今のは……。
その、取り乱してしまいました」
相模は、俺のもたれる本棚とは対に当たる棚に背を合わせ、いわゆる お姉さん座りで向い合った。
肩を上下に揺らしていて、どうやら、息を切らしているようだ。
今の言動に、そんな疲れるところがあったか?
いや、相模は驚くほど細い。さっき、俺に乗っかるような体勢になった時も、身体の中身がすかすかなのではないかと疑うほど軽かった。
その身体に先ほどのような激情が迸るというのは、彼女にとって相当な負担になるのかもしれない。
そもそも、そんな身体でよく学校に来れるな、と少し心配になる。
「でも、私をこんな偏屈な女にしたのは紛れもなくあの人です。こうなりたくなければ、__いえ、なってはいけない、だから…あの人から離れてください」
俺は、相模と視線を絡ませて、動じない心を保つことを心掛けた。
「相模さん」
「なんですか」
「あの人って、やっぱり
“明石 ひな乃”のこと?」
相模は、答えなかった。
それから俺は、相模と図書室で別れ、家に直帰した。そして、自室の勉強机に課題を並べて、にらめっこする。
あのあと、あの蔵書室に寄ったのだが、ひな乃の姿がなかったのだ。
別に毎日必ず会う約束をしているわけではないので、ひな乃が部屋にいない時は間々あるし、逆に俺が寄らない時もある。
一応、行けないという旨は伝えに行くが、ひな乃の方はそういうことに無頓着なのか、俺にわざわざ連絡することはない。
__連絡。俺は、ひな乃の連絡先を知らない。
あの部屋で、お互い携帯をいじることもなかったので、交換する成り行きに至らなかったのだ。
あの部屋以外でひな乃と会うことに俺は執着してないので、気にも留めていなかったが……今は、連絡先を含めて、ひな乃のことをもっと、知りたいと思う。
多分、先週の出来事がきっかけだろう。
ひな乃が具合悪そうにして、俺を頼ってくれた時、自分の中にある、彼女への気持ちに気付いたのだ。
しかし、それは円谷が言うような、色恋と呼ぶほど確かではなく、かと言って友情だとか、家族のような愛情などとは、また、違う気がする。
なんにせよ、ゆっくり見極めていけたらいい__そんな風に思う。