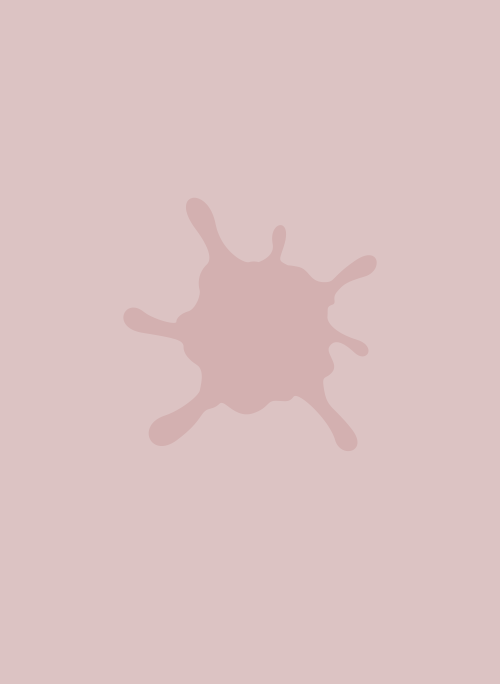それから十数分が経った頃、ひな乃は煎れたての紅茶を盆に載せて運んできた。
「先輩は、紅茶がお好きでしたよね」
「…毎日のようにここに来て飲んでるのがその証拠だ」
なんだか気恥ずかしくなり、ひな乃から目を逸らした。
「ふふ、そうですよね」
ひな乃の笑い声に慌てて視線を戻したが、ひな乃は笑っていなかった。
冷酷なくらいに真顔で、そんな顔してふふと言うことに、苦笑いした。
「ひな乃も、好きなんだろ」
「__さぁ…。どうでしょう」
おかしな回答だ。ひな乃も俺がここに来た時は必ず飲んでいるではないか。
俺は、ティカップに口をつける。
鼻腔を突き抜ける甘みを含んだ爽やかな薫り。
2日間飲んでいなかっただけなのに、とても久しい気がする。
「お味はいかがでしょうか」
「うん、今日もすごく美味しいよ」
俺がそう言うと、ひな乃はクスリとも笑わず、視線を絡ませロックオンする。
「砂糖とミルクは要りますか」
「…要らない」
ひな乃はそこで、ようやく俺から視線を外し、自らも紅茶に口をつけた。
喉が、微かに上下するのが見える。
ゴクリ。俺は唾を飲んだ。
至福のひとときを味わうひな乃は天使のように美しく、仕草のひとつひとつが艶っぽい。
子どもっぽい髪型に合わないようなフェロモンが出ていて色気がある。
ひな乃の柔らかい眼差しは、紅茶に向けられていてどこか恍惚としていた。
__その視線を、俺にも向けて欲しい。
そんな風に、思う自分がいた。
そして、口を衝いて出た言葉。
「今度 家に来ないか」
「__え?」
「あ、いや、その疚しい意味じゃなくて……うち、父親が紅茶とか好きでよく飲んでるから、色んな種類の飲めるからその、えっと」
言い出しっぺは自分なのに、ひどく狼狽してしまった。
女の子ひとり誘うのに、ドギマギしてしまうのが情けない。
俺は、冷汗三斗の思いで言葉を紡ごうとするが、巧く取り繕えない。
__また、ひな乃の機嫌を損ねてしまうかもしれない。
しかし、ひな乃は意外にも、唐突な俺の申し出に、度肝を抜かされたようで、眉を顰めて不思議そうに首を傾げていた。
「日にちにもよりますが、先輩は、お忙しいのでは」
これは予定が合えば平気ということなのだろうか。
「あー…今週の日曜とか、どう?
俺は、ひな乃が思うほど別に忙しくない」
初デートに彼女を誘う彼氏みたいな気分になり、心拍数が上がるのを感じる。