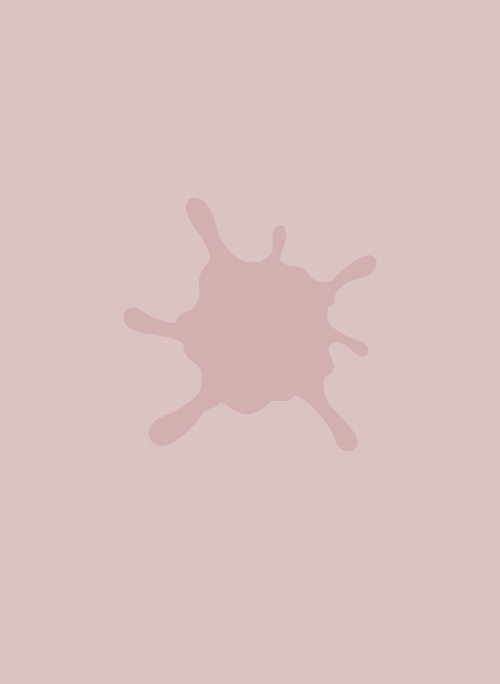「えー。人気が無かったら傾園の美女とお話する機会すらないだろ」
「でも、ひな乃は気まぐれなんだ。人気云々の問題じゃないと思う」
「ちがうね。駿河の甘〜いマスクにやられたからだっ」
なんだか話が嫌な方向に進んできたので、俺は円谷に構わず昼休み後の授業に必要な教材を準備し出した。
窓から外の空を見ると、まだこの辺は晴れていたものの、遠くに暗雲が立ち込めていた。
…俺に人気が無いのは、ほんとうに、事実である。
今日日、家柄家柄言っているのは時代錯誤で、実力が重視されている社会に成り代わっているが、
それでも駿河は有名過ぎる故に、人気どころか周りの者のほとんどが、他人行儀なのだ。
両親、特に母親が教育熱心なため、常に賢くあることを俺に要求し、物心ついた頃から勉強に奮励してきた。
そんなこともあり、友人関係を築く大切な段階をすっ飛ばして高校生になってしまった。
__だから俺は、名門中の名門である清條院に入学した。
この清條院学園には、すべての学年でおよそ500名の生徒が在籍している。
その内、名家の出身、つまり御曹司、または令嬢にあたる者は、1割から2割程だと言われている。
この学園は、いわゆる“金持ち校”で、入学金や学費は馬鹿にならず、特待生として通うならまだしも、一般のコースだと莫大な資金が要る。
たいていの生徒は、大企業の子息とまではいかなくとも、そこそこ財産を蓄えた家の出身である。
それを知った俺は、清條院に望みを掛けた。
現実はそう甘くなく、悲しいことにここでも俺は浮いてしまった。社交性の低さが、そうさせた。
だが、前よりは幾分もマシだと思う。
以前は、円谷のようなクラスメイトは居なかったし、後輩のひな乃も基本、俺の家柄を意識していない筈だ。
「いや〜、でもいいなぁ」
円谷は、若干声を潜めて続ける。
「ここの学園、あんまり色恋沙汰とか聞かないから駿河が羨ましい。
名家の生まれって、自由に恋愛すらできないの?
俺はフツーの家だから、その概念は理解しかねる」
確かに、以前通ってた私立中学よりも、清條園では、艶聞は少なく感じられる。
誰かと付き合ったとかがバレると親に良い顔をされないからかもしれない。
今時、政略婚とかは聞かないけど、人付き合いも慎重に行わなければいけないのだろう。
「言っとくけど、ひな乃も相模も、そんな関係じゃないからな。ひな乃は後輩で、相模は__…ただの同級生だ」
相模が“この学園で人と関わるな”と俺に警告したことを思い出す。
相模が言っていた、先ほど談笑していた友人とは、円谷のことだろう。つまり円谷ともこんな風に話してはいけないのだ、相模が言うには。