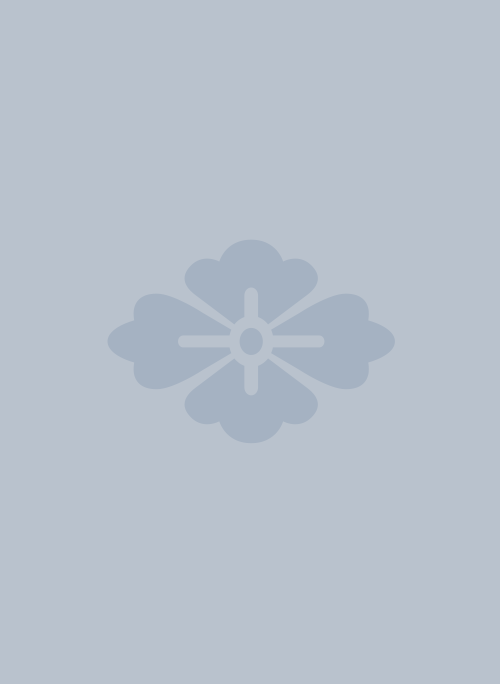翌日のことでした。門外で、車馬の賑やかな音がしました。門番が来客の意を伝えると、大君は東閣で彼らを迎えました。集まったのは文人ばかりでした。席上、大君は昨夜の私たちの詩を披露しました。人々は、皆、感服し、
「大君はいったい何処で、このような名作を手に入れられたのでしょうか?」
と尋ねました。大君は微笑みながら、
「童僕(子供の召使)が外に出掛けたとき、路上で拾ったものだ。恐らく、近郊の才子の手によるものだろう。」
と応えましたが、皆、納得いかないようでした。そうしたなか、遅れてやってきた成謹甫さまが、私たちの詩を御覧になって次のように言いました。
「これらの詩は風格が清雅で気高い想いあふれ、俗世の色彩がまったく見られません。作者たちは、宮中の奥深いところに暮らし、俗人と交わることなく、いにしえの詩を学び、日夜吟じているのでしょう。」
そして、私たちの作品を一つ一つ評したのち
「……願わくは大君が御隠しなさっている仙女十名を臣等にも会わせて頂きたく思います。」
と結びました。大君は謹甫さまの洞察力に、たいそう感服なさいましたが、そうした素振りは少しもお見せになられず、
「誰が汝に詩評を命じたか。我が宮中に、そのような者が居るわけがないだろう。つまらぬことを申すな。」
と躱(かわ)されました。
私たちは戸の隙間から聞こえてくる、こうした言葉に耳を傾けていましたが、皆、感嘆するばかりでした。
その夜、紫鸞が誠意に満ちた口調で私に問い質しました。
「女として生まれたのだから、お嫁に行くことを望むのは当たり前のことよね。あなたの想い人が誰だかは分からないけれど、日々、やつれていく姿を見るのはつらいことよ。私に話してはくれないかしら。」 彼女の心遣いを有り難く感じた私は立ち上がって謝意を述べたのち
「宮中は人が多くてうっかりしたことは言えないので、今まで黙っていたけれど、あなたがそれほどまでに私のことを気に掛けてくれているようなので話すことにするわ。」
と胸の内を打ち明けることにしました。
「大君はいったい何処で、このような名作を手に入れられたのでしょうか?」
と尋ねました。大君は微笑みながら、
「童僕(子供の召使)が外に出掛けたとき、路上で拾ったものだ。恐らく、近郊の才子の手によるものだろう。」
と応えましたが、皆、納得いかないようでした。そうしたなか、遅れてやってきた成謹甫さまが、私たちの詩を御覧になって次のように言いました。
「これらの詩は風格が清雅で気高い想いあふれ、俗世の色彩がまったく見られません。作者たちは、宮中の奥深いところに暮らし、俗人と交わることなく、いにしえの詩を学び、日夜吟じているのでしょう。」
そして、私たちの作品を一つ一つ評したのち
「……願わくは大君が御隠しなさっている仙女十名を臣等にも会わせて頂きたく思います。」
と結びました。大君は謹甫さまの洞察力に、たいそう感服なさいましたが、そうした素振りは少しもお見せになられず、
「誰が汝に詩評を命じたか。我が宮中に、そのような者が居るわけがないだろう。つまらぬことを申すな。」
と躱(かわ)されました。
私たちは戸の隙間から聞こえてくる、こうした言葉に耳を傾けていましたが、皆、感嘆するばかりでした。
その夜、紫鸞が誠意に満ちた口調で私に問い質しました。
「女として生まれたのだから、お嫁に行くことを望むのは当たり前のことよね。あなたの想い人が誰だかは分からないけれど、日々、やつれていく姿を見るのはつらいことよ。私に話してはくれないかしら。」 彼女の心遣いを有り難く感じた私は立ち上がって謝意を述べたのち
「宮中は人が多くてうっかりしたことは言えないので、今まで黙っていたけれど、あなたがそれほどまでに私のことを気に掛けてくれているようなので話すことにするわ。」
と胸の内を打ち明けることにしました。