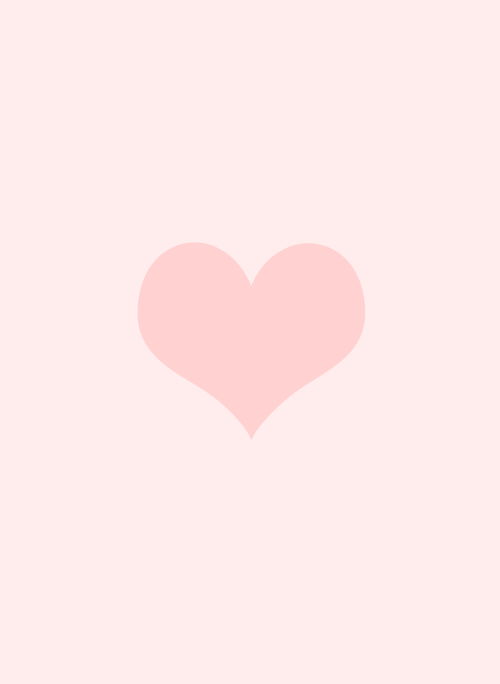「好きだったんですよ、亜希……あなたのこと」
重くなった空気を軽くしようと、俺は努めて爽やかにそう言っていた。
俺のそんな言葉に、志乃さんは二重の目をぱちぱちとさせて俺を見る。
志乃さんが気まずい思いをすることなんてない。
俺はそんな思いを込めてニコッと笑ってみせた。
「何にも思い出さないかもしれないって思ってたし。ちょっと……希望見えたっていうか」
亜希が志乃さんのことを思い出したのか、忘れていなかったか、それはいまだに不明だ。
でもそれを聞いて、一筋の光が見えたような気がした。
これから、亜希は今までのことを少しずつでも思い出すかもしれない。
俺にはそんな希望に思えた。