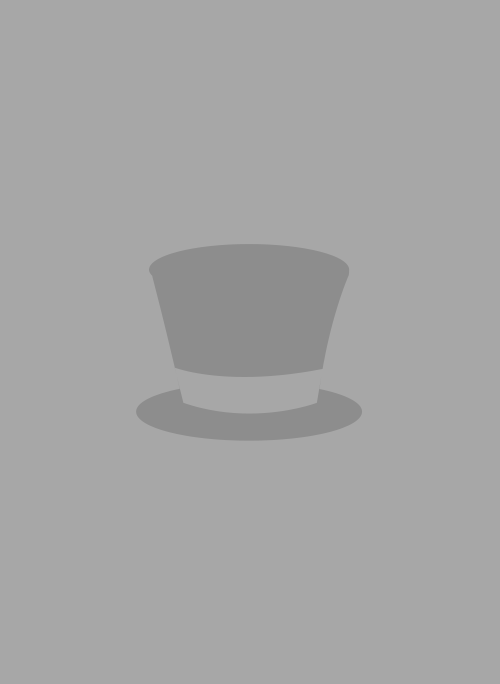足が地面から少しずつ離れ始めた時、茶色の長い髪が見えた。
制服姿の諸星さんだった。
彼女は柵から身を乗り出し、僕の腕を掴んだ。
「違うの!こーゆーことじゃない。川本君には幸せになってもらいたい。」
何を言っているんだろう……
「川本君に死んでもらいたくてあの動画を作ったわけじゃない。想いが通じた。それで十分。」
彼女は泣きながら笑った。
「ありがとう……!」
辺りは眩しくなり僕は目を閉じた。
制服姿の諸星さんだった。
彼女は柵から身を乗り出し、僕の腕を掴んだ。
「違うの!こーゆーことじゃない。川本君には幸せになってもらいたい。」
何を言っているんだろう……
「川本君に死んでもらいたくてあの動画を作ったわけじゃない。想いが通じた。それで十分。」
彼女は泣きながら笑った。
「ありがとう……!」
辺りは眩しくなり僕は目を閉じた。