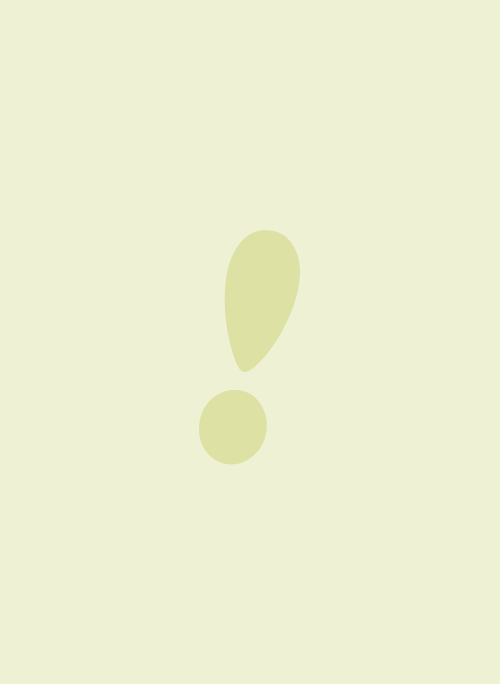インターホンが鳴って出て行くと、尊琉君がそこにいた。
怒ってるかな……。
「おはよ」
「あ、おはよ……」
恐る恐るドアを開けたものの笑顔の尊琉君がいて、少し拍子抜けだ。
怒って……ない?
「上がって?」
「うん。お邪魔します」
玄関のくつを見てみたらお兄ちゃんのくつがいつのまにか無くなっていた。
いつ出て行ったのかわかんないけど、よかった、いなくなってて。
部屋に上げて、飲み物とお菓子を一緒に出した。
時計に目をやると、1時半を回っている。
「ねぇ尊琉君、昨日私がメール送った時、どこにいた?」
「どこって……家にいたけど」
「ずっと?」
「うん」
じゃあお兄ちゃんが言ってた人ってもしかして尊琉君じゃない?
様子もいつもと一緒だし、家にいたって言ってるし。
でも、だとしたら誰のこと言ってたんだろ。
「どうして?」
「ううん、何でもない。さ、どんどん食べて」
大量にあるお菓子の袋を片っ端から開けると、「ありがとう」と言って尊琉君はそれに手をつける。
私は食欲ないからいらないなぁ。
「もしかして、ダイエットとか考えてるんじゃねぇだろうな?」
「そんな訳ないでしょっ。ご飯食べたのがさっきなの。空いてきたら私も食べるから、残しといてねっ」
ご飯なんか食べてないけど、起きてから何も食べてなかったけど、言ったらまた心配かけるからな……
「はいはい。わかりました」
尊琉君が笑ってくれていて、一安心だ。ホッとしているのに対し、どこか落ち着きがない自分。
けれど尊琉君には気づかれないようにしていた。