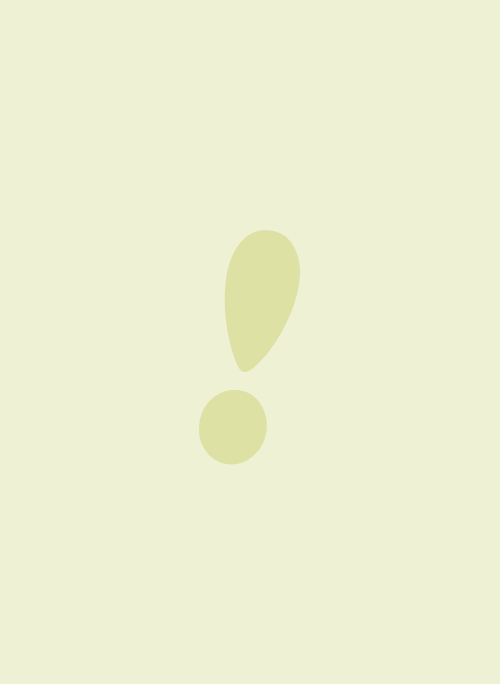お母さんに声をかけて、玄関へ向かう。
学校に行きたくなかったけど、行かないままだとどうなるかわからないし。
無理矢理にでも行くしかない。
重い足取りでドアを開けると――……
「おはよ」
聞こえないはずの声が、耳に届いた。
「ど、どうして……?」
腕を組んで壁に寄りかかっていたのは、尊琉君だ。
「また、泣いてるんじゃないかと思って。迎えに来た」
「な、泣いてはないけど……」
視線が自然と下を向く。
尊琉君は私の顔を覗き込むように見た。
「泣いてはないけど?」
どうしてここまで、優しくしてくれるの?
私の気持ちも伝えて、尊琉君に酷いこしたのに……
そんなことされたら――……
「また泣きそう……」
目頭を押さえながらクスクス笑うと、私の手を引く尊琉君。
「行くぞ」
「うん」
不思議なくらい、胸の中が軽くなっていた。