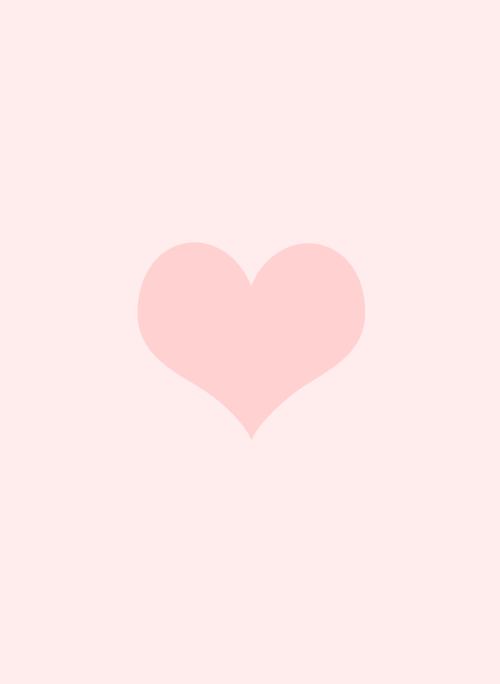「君みたいな優秀な秘書官がいて私も幸せだよ。我儘は言ってみるものだね」
総統になった坂月は、補佐官の一人に如月を据えた。
本来、総統の補佐官は佐官級以上のものが就くのが通例で、大尉である如月はまさに異例の存在。
それを押し切ったのはこの男。
そして、その根回しをしたのは俺自身。
考えて、考え抜いて出した結論が間違うはずがない。
それでも、こうして何度も繰り返し問う。
これで良かったのだろうかと。
考えてもどうしようもないとわかっているはずなのに。
如月の頬を赤く染めはにかむ姿を見ながら、やっぱり間違ってないと無理やり考えを打ち切った。
二人の会話の邪魔をしないように静かに退室の礼を取ると、男は呼び止める。
「一色君。今日はもう仕事は構わない。如月君もね」
男の真意を確認するため視線を上げるが、如月が視界に入る。
彼女を見た瞬間に置き去りにしてきた時が遡る。
思い出すこともしなかった、過去に。
驚いた顔で男を見つめる如月の顔は、さきほどの会話のせいか暖炉の炎のせいなのだろうか。
いつも以上に温かく優しげに俺の目に映り、昔の手の冷たさを思い出させたのだ。
何かがこみ上げてきた。
何かが。
それが何かがわからず。
わからないけど、何かがこみ上げて。
それが口を突かないように、ごくりと息を呑んだ。