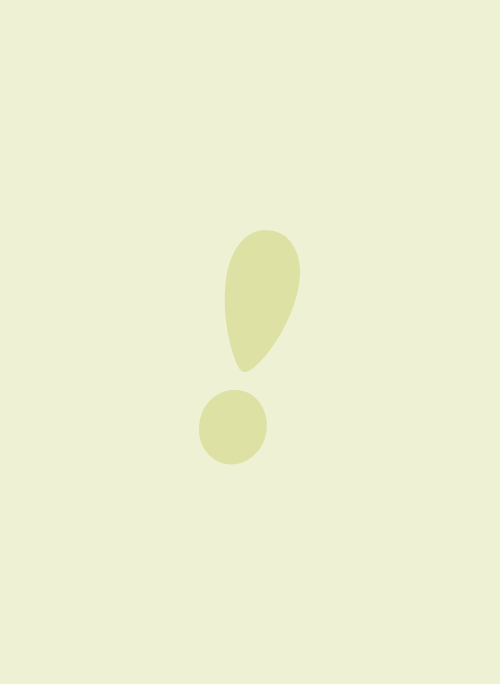「お話でも、どうかな?」
曇り空のある朝、王子様が廊下を散歩している途中です。
あの日のおじさんとまた出会いました。
今度は腕のみの移動ではなく、車椅子に乗っています。
「少し、誰かと話したくなったんだ。
娘は診察中でね。。他に話し相手もいないから、ものすごく暇なんだ。付き合ってもらえないだろうか?」
「え?…あ、…分かった……」
どもりながらも断る理由が考えられなかった王子様は、しぶしぶうなずきました。
そのままクラゲの水槽があるロビーに移動。
ふよふよ浮かぶ青いクラゲを、長椅子に腰掛け見つめます。
「あ、あのさ。あの子、そんなに悪いの?」
珍しいことに、話を切り出したのは王子様の方です。
緊張のあまり手はぶるぶる。
頭には汗が滲んでいます。
それに気づかない様子で、おじさんはうなずきました。
「身体上の異常は見受けられないがね。
昨日言った通り、彼女は人の顔を認識することが出来ない。視力は特に問題はない。ならば精神に異常が出ているかもしれないんだ。」
「精神に?」
「ああ。何か強いストレスやショックがあるのかもね。
でも本人自身それらのことを覚えていないから、分からないんだ。
多分、幾年か前に事故に遭った時に、記憶が吹き飛んだんだと思う。」
「……事故って、何が起こったの?」
そう王子様が聞くと、おじさんは少し表情を曇らせました。
「大きな車に轢かれたんだ。その時家に帰る途中でね。
何とか庇ったんだが、衝撃を遮ることはできなかった。
この足もその時限りで動かなくなった。」
そして、目を少しだけ閉じます。
「娘は幸い無傷だったが、三日間の間昏睡していた。
そして、目覚めた頃には自分を含め他人が誰なのかを判断できなくなっていた。
医者に、記憶喪失に似たようなものだと言われたが、そんなものじゃない。
彼女にちゃんと記憶はある。指摘を受けなければ思い出さないだけなんだよ。
……そう考えてたんだ。そう思っていたんだ……。」
突然、おじさんは震えだしました。
唇をぐっと噛み締めています。
「しかし最近になって、彼女の記憶力は急速に低下し始めた。顔は名前があれば認識できるけど、番号や昨日や一昨日といったものはもう覚えてすらいない。彼女が記憶の底に隠せるのは人の顔だけになってしまったんだ。これさえも思い出せなくなったら、もう彼女はきっと空っぽになってしまう。」
曇り空のある朝、王子様が廊下を散歩している途中です。
あの日のおじさんとまた出会いました。
今度は腕のみの移動ではなく、車椅子に乗っています。
「少し、誰かと話したくなったんだ。
娘は診察中でね。。他に話し相手もいないから、ものすごく暇なんだ。付き合ってもらえないだろうか?」
「え?…あ、…分かった……」
どもりながらも断る理由が考えられなかった王子様は、しぶしぶうなずきました。
そのままクラゲの水槽があるロビーに移動。
ふよふよ浮かぶ青いクラゲを、長椅子に腰掛け見つめます。
「あ、あのさ。あの子、そんなに悪いの?」
珍しいことに、話を切り出したのは王子様の方です。
緊張のあまり手はぶるぶる。
頭には汗が滲んでいます。
それに気づかない様子で、おじさんはうなずきました。
「身体上の異常は見受けられないがね。
昨日言った通り、彼女は人の顔を認識することが出来ない。視力は特に問題はない。ならば精神に異常が出ているかもしれないんだ。」
「精神に?」
「ああ。何か強いストレスやショックがあるのかもね。
でも本人自身それらのことを覚えていないから、分からないんだ。
多分、幾年か前に事故に遭った時に、記憶が吹き飛んだんだと思う。」
「……事故って、何が起こったの?」
そう王子様が聞くと、おじさんは少し表情を曇らせました。
「大きな車に轢かれたんだ。その時家に帰る途中でね。
何とか庇ったんだが、衝撃を遮ることはできなかった。
この足もその時限りで動かなくなった。」
そして、目を少しだけ閉じます。
「娘は幸い無傷だったが、三日間の間昏睡していた。
そして、目覚めた頃には自分を含め他人が誰なのかを判断できなくなっていた。
医者に、記憶喪失に似たようなものだと言われたが、そんなものじゃない。
彼女にちゃんと記憶はある。指摘を受けなければ思い出さないだけなんだよ。
……そう考えてたんだ。そう思っていたんだ……。」
突然、おじさんは震えだしました。
唇をぐっと噛み締めています。
「しかし最近になって、彼女の記憶力は急速に低下し始めた。顔は名前があれば認識できるけど、番号や昨日や一昨日といったものはもう覚えてすらいない。彼女が記憶の底に隠せるのは人の顔だけになってしまったんだ。これさえも思い出せなくなったら、もう彼女はきっと空っぽになってしまう。」