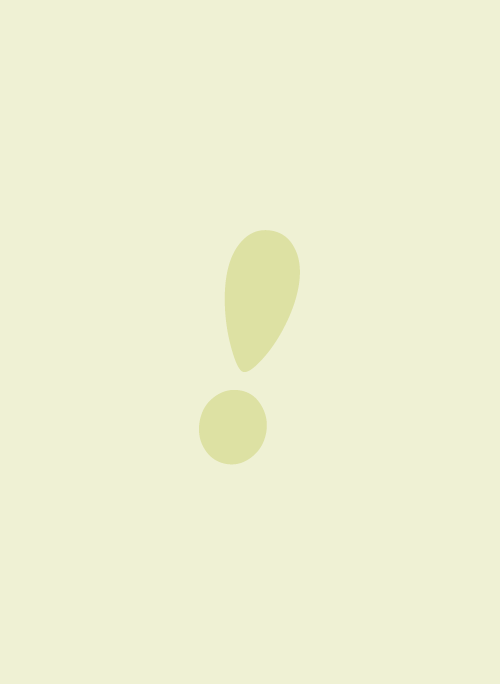いえいえ、芋虫なのは王子様の勘違い。
正体は、うつ伏せて足を引きずりながら腕のみで進むおじさんです。
額に汗を浮かべながら、彼は腕二本を足代わりにして前進していました。
その様子はとても苦しそうです。
何か発作を起こしているのかと王子様は心配になりました。
躊躇もなくおじさんに近づき、震える声で尋ねます。
「……あの、おじさん。先生呼ぶ?」
ですが、おじさんは首を振りました。
ゼエゼエと息を切らしながら、王子様に問いかけます。
「君、女の子を見なかったか?笑顔の可愛らしい天使のような子だよ。あと、自分の名前を忘れるほどの忘れんぼなんだ……」
「彼女なら屋上にいるよ。」
王子様がそう非常階段を指差しました。
それを見ておじさんはくそっ、と床を拳で叩きつけます。
「こんな時足が動いたら……」
王子様は正直困りました。
彼女を此処に連れていくべきか。
いえ、知らない人なので連れていこうとしたら変質者と叫ばれるでしょう。
そんな羞恥は耐えられません。
おじさんを連れていくべきか。
いえ、体力のない王子様は担ぎ上げようとしたら逆に潰れるでしょう。
悩んでいると、おじさんは唸りながら上体を起こしました。
ドアから少し離れ、廊下の壁に寄りかかり、一息をつきます。
「ここで少し休憩だ。」
そして、王子様に質問するのでした。
「君はここの患者かい?」
王子様は戸惑いながらもうなずきます。
おじさんはそうか、と苦笑します。
「実は、この病院に来たのはつい一昨日のことなんだ。多少半身不随で無理をしすぎたようでね。
道行く途中で意識が飛んでしまった。」
と、そこで心配するような目付きで王子様を見据えます。
「君は?どこか悪い所があるのかい?」
王子様はさぁ、と首をかしげることしかできませんでした。
怪我もしていないし、病気だってしていない。
なのにどうして此処にいるのでしょう。
するとおじさんは半ば同情的な眼差しになりました。
「君の両親は優しいんだね」と。
病気であることを親に隠された子供だと勘違いされたのでしょう。
しかし、王子様は親のことなど覚えていません。
気が付いたら病院で暮らしていた。
ただそれだけなのです。
同情されたとはいえ人間関係に無関心な王子様。
あまり傷つくことはありませんでした。
「しかし、比べて私はダメな父親だよ。
あの子を事故から守ることさえできなかったんだ。」
感傷的な気分になった顔で、おじさんは言葉を継ぎます。
「あんな感じでも、昔は一度出会った人の顔を覚えるのはとても得意な子だったんだよ。でも今や、出会った人の顔を認識することはできない。名前を言わない限り、気付いてもらえないんだ。
あなたは誰、と実の娘に言われるほど辛いことはなかったよ。
しかしこれもあの子を守れなかった私への罰だ。」
そうだったのか……と王子様は納得しました。
相手の顔を認識できないからあんな反応だったのか。
まぁ、忘れられたに決まってるけど。
我にかえったかのように、おじさんは謝罪します。
「すまないね。子供相手に全く関係のない話をして、私はやはりダメな大人だよ。
今の話は忘れておくれ。」
そして、王子様に笑いかけました。
「同じ病院の患者として、色々な迷惑をかけてしまうかもしれない。
だが君も何か困ったことがあったら言ってくれ。脚は動きはしないが、手先は器用なんだよ。
仲良くしてもらえないだろうか?」
おじさんはきっと機械を扱う仕事をしているのでしょう。
差し出されたごつごつの手には、黒い油の色が染み込んでいます。
王子様は恐る恐る、折れそうな手でそれを握りました。
何年ぶりかの握手でした。
正体は、うつ伏せて足を引きずりながら腕のみで進むおじさんです。
額に汗を浮かべながら、彼は腕二本を足代わりにして前進していました。
その様子はとても苦しそうです。
何か発作を起こしているのかと王子様は心配になりました。
躊躇もなくおじさんに近づき、震える声で尋ねます。
「……あの、おじさん。先生呼ぶ?」
ですが、おじさんは首を振りました。
ゼエゼエと息を切らしながら、王子様に問いかけます。
「君、女の子を見なかったか?笑顔の可愛らしい天使のような子だよ。あと、自分の名前を忘れるほどの忘れんぼなんだ……」
「彼女なら屋上にいるよ。」
王子様がそう非常階段を指差しました。
それを見ておじさんはくそっ、と床を拳で叩きつけます。
「こんな時足が動いたら……」
王子様は正直困りました。
彼女を此処に連れていくべきか。
いえ、知らない人なので連れていこうとしたら変質者と叫ばれるでしょう。
そんな羞恥は耐えられません。
おじさんを連れていくべきか。
いえ、体力のない王子様は担ぎ上げようとしたら逆に潰れるでしょう。
悩んでいると、おじさんは唸りながら上体を起こしました。
ドアから少し離れ、廊下の壁に寄りかかり、一息をつきます。
「ここで少し休憩だ。」
そして、王子様に質問するのでした。
「君はここの患者かい?」
王子様は戸惑いながらもうなずきます。
おじさんはそうか、と苦笑します。
「実は、この病院に来たのはつい一昨日のことなんだ。多少半身不随で無理をしすぎたようでね。
道行く途中で意識が飛んでしまった。」
と、そこで心配するような目付きで王子様を見据えます。
「君は?どこか悪い所があるのかい?」
王子様はさぁ、と首をかしげることしかできませんでした。
怪我もしていないし、病気だってしていない。
なのにどうして此処にいるのでしょう。
するとおじさんは半ば同情的な眼差しになりました。
「君の両親は優しいんだね」と。
病気であることを親に隠された子供だと勘違いされたのでしょう。
しかし、王子様は親のことなど覚えていません。
気が付いたら病院で暮らしていた。
ただそれだけなのです。
同情されたとはいえ人間関係に無関心な王子様。
あまり傷つくことはありませんでした。
「しかし、比べて私はダメな父親だよ。
あの子を事故から守ることさえできなかったんだ。」
感傷的な気分になった顔で、おじさんは言葉を継ぎます。
「あんな感じでも、昔は一度出会った人の顔を覚えるのはとても得意な子だったんだよ。でも今や、出会った人の顔を認識することはできない。名前を言わない限り、気付いてもらえないんだ。
あなたは誰、と実の娘に言われるほど辛いことはなかったよ。
しかしこれもあの子を守れなかった私への罰だ。」
そうだったのか……と王子様は納得しました。
相手の顔を認識できないからあんな反応だったのか。
まぁ、忘れられたに決まってるけど。
我にかえったかのように、おじさんは謝罪します。
「すまないね。子供相手に全く関係のない話をして、私はやはりダメな大人だよ。
今の話は忘れておくれ。」
そして、王子様に笑いかけました。
「同じ病院の患者として、色々な迷惑をかけてしまうかもしれない。
だが君も何か困ったことがあったら言ってくれ。脚は動きはしないが、手先は器用なんだよ。
仲良くしてもらえないだろうか?」
おじさんはきっと機械を扱う仕事をしているのでしょう。
差し出されたごつごつの手には、黒い油の色が染み込んでいます。
王子様は恐る恐る、折れそうな手でそれを握りました。
何年ぶりかの握手でした。