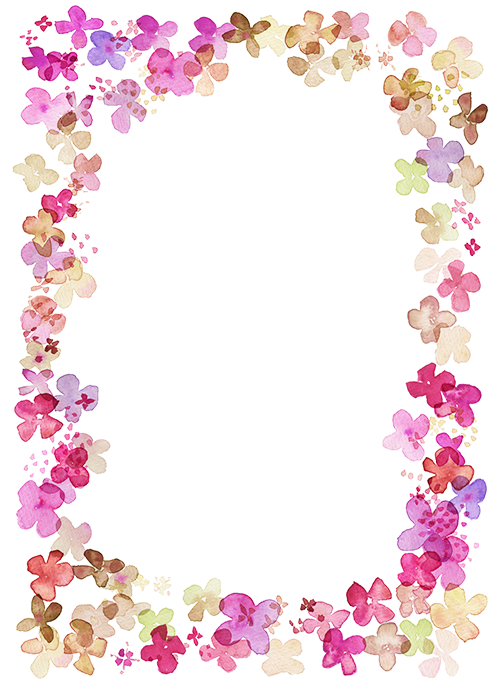黒い車のヘッドライトが、陽斗くんに反応して一瞬光って。
スーツのジャケットを腕にかけた陽斗くんは、
運転席ではなく後ろのドアに手をかけた。
上半身を潜らせて、何やら探しているような背中。
開いたドアに隠れて、見えない彼の手元。
レオンの振るしっぽの振動を肌に感じながら、ぼんやり眺めていると。
「これ。」
振り返った彼が、差し出したもの。
小さな・・・パスケース。
青地に白く象られた、planetのロゴ。
指し示す日付は。
来週、日曜のdate。
簡単そうに、見せるけど。
簡単なことではないと、本能が察知する。
『陽斗くん、』
「スタッフパス。航から、もらったことなかった?」
首を振る。唇を、噛む。
心臓が音を立てて、鳴り始めたのに気づく。
彼は、確信の。
蓋を開ける準備をしている。
「そっか。俺、スタッフ用の通用口とかがよく分からないんだけど。
瀬名さんに頼んでおくから、彼女から聞いてもらえる?」
『ねぇ、陽斗くん、』
二歩も、三歩も。
いつの間にか空いていた距離を、彼が私へと縮める。
ふわっ、と。
彼の腕が持ち上がったと思うと。
『・・・!』
首にかけられたその重みが、私の言葉を塞いだ。
「会いに来て、これで。
ライブが終わったら、航じゃなくて俺のとこに来て。」
滲みそうになる、視界を。
彼が去るまでは、負けたくない。
何か口にすれば、溢れてしまいそうに溶け出した感情。
「待ってる。俺のとこに来てくれるなら、どんな理沙子でもいいから。」
そんな愚かな私にさえももう気づいていて。
受け止めると覚悟している、熱い瞳。
この人は、きっと。
私のずるさも弱さも傲慢さも。
自分が引き受けると、言ってる。
「他の男を追って、ニューヨークになんて行かせない。一緒にいて、俺と。」
息が、あがる。
だって、これは。
「__________________一緒に生きよう、俺と。」
人生で、そう何度もは受けることのできない。
熱い、告白だ。