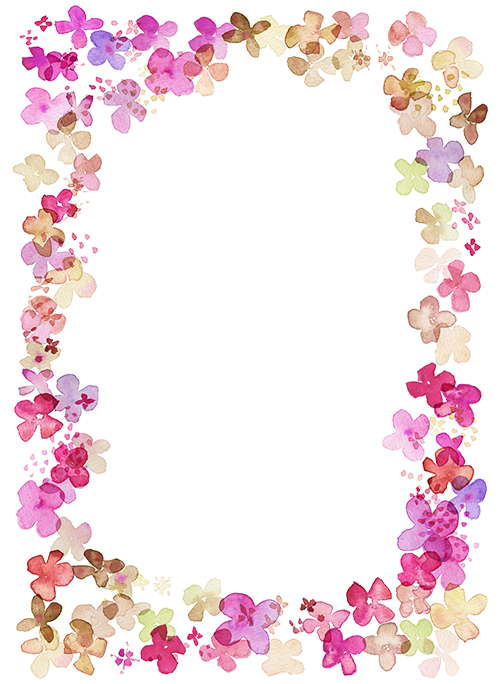ふわっ、と。
彼の気配が近くなったことを、肌で感じた。
私の向かいに座っていたはずの陽斗くんは。
今、この部屋のどこにいるんだろう。
「俺、理沙子のこと好きって言ってるのは。今だけの気持ちで、言ってるつもりはないよ。」
『うん・・・。
ごめん、そういうつもりで言ったんだじゃないよ。自分の仕事に、悩みがあって。』
「悩みって、なに?」
『私の仕事は、いつまでもだらだらできる仕事じゃないでしょ。
そろそろ、本格的に踏み込むか、辞めるか、決めないといけない歳なんだよ。』
「だから、それは」
『ありがとう、陽斗くんの言いたいことは何と無く分かってるから。』
彼が今夜開いてしまいそうな真相を。
言葉を遮ることで、無理やり蓋をしようとしたら。
一瞬、しんと。
空気が、冷えた。
「“何と無く”か。」
低い、呟きに。
彼の気配の濃さが、変わった気がした。
「じゃあ、はっきり分からせるよ。」
一段と近くなった声が。
怖くて、逆に。
距離を確かめたくて、手を伸ばす。
「任せてよ、理沙子の人生。
___________________俺に。」
掴まれた、手首。
熱い手の平。
ふと、頬のあたりで感じたBVLGARIの香りに。
もしも、この香りが彼の腕から溢れているのなら。
私はもう、ソファの背もたれまで追い詰められているのかもしれないと思う。
生温かさを、音を立てて飲み込んだら。
「どこにも行くな。
もうずっと、俺のそばだけにいてよ。」
あまりにも。
彼の声が、近いと感じた。
次に降ってきた、赤い果実は。
陽斗くんの、唇だった。