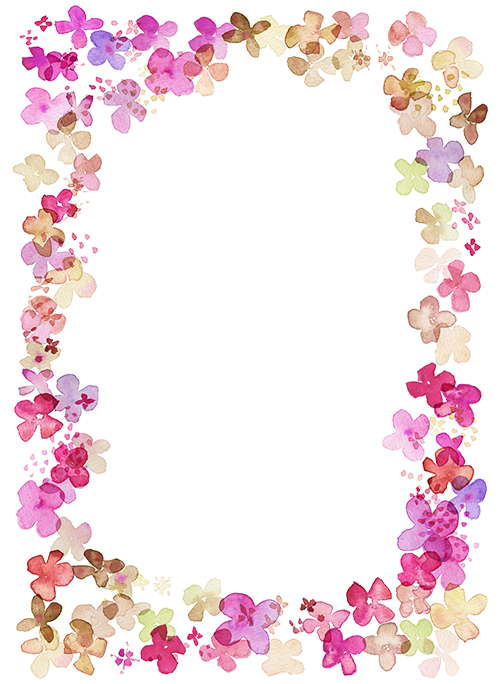『冷たいおしぼりお願いします。』
隣から声が聞こえ、はっとした。
やばい、こんな席で絶対居眠りなんてできない。
『お疲れさまです。おしぼり、ちょっと首にあててもいいですか?』
隣を見ると、小柄な女の子が両手におしぼりを広げていた。
『私も眠たくなると、よくするんです。けっこう効きますよ?』
小首を傾げて、いたずらに微笑んだ。
「・・・あ、すいません、退屈だったわけじゃなくて。」
『分かってますよ、大丈夫。_____えい』
彼女がピタっと首の後ろにあててくれたおしぼりの冷たさで、一瞬で目が覚めた。
「うわー・・・すげえ。効くな・・・。ありがとうございます。」
『ね?起きたでしょ?』
覗きこむように笑った笑顔に、息を飲んだ。
やばい。この子、めちゃくちゃ可愛い。
透明感の塊みたいな。
真っ白な肌は発光してるようにキラキラしていて、大きな黒目が小動物を思わせた。
なのに。
溢れ出る色気。
いつから、ここに座ってたんだろう?
『けっこう飲んできました?目がうるうるしてる。』
深く黒い瞳は、俺の、何もかもを見透かしそうな気がした。
なんだこの感覚。
深い穴に落とされてしまいそうになるのを、必死で足を踏ん張って抵抗しているような感覚。
『早く帰れるように、出来るだけ巻きますね。』
ちらっと倫さんの方を見て、ドレスの裾を掴んで俺の隣を立とうとした彼女。
「・・・あ、ちょっと待って。」
咄嗟に手首を掴んでしまった。
「・・・すいません。・・・名前、聞いてもいいですか?」
あひる口でニコっと笑った。甘い香りにクラクラした。
『理沙です。じゃあ、私も質問。おいくつですか?』
「23です・・・」
やった、と目を細めて笑った彼女。
『当たった!タメですね、私たち。』
俺の目の奥を覗きこむようにしてそう言ったあと、俺の返事を待たずに立ち上がった彼女は、ママさんに代わり倫さんの隣に座った。
「彼女が、俺が長年可愛がってる秘蔵っ子」
帰りの車の中で、倫さんが教えてくれた。
夜の世界で働く前から、倫さんとは付き合いがあるということ。
あの若さで、あの高級店で、入店間も無くして既にナンバー3に入っているらしいということ。
「惚れるなよ。って、大丈夫か。」
笑う倫さんに、「はい」と返事をして何となく俺も笑った。
俺には、愛する人がいる。
大丈夫だ。
次第に、倫さんなしでも店に訪れるようになった。
さすがの高級店、そんなに頻繁には行けなかったけど。
相変わらず、甘い目眩を与えてくる彼女に油断はできなかったけれど。
一般人→芸能人への過渡期の俺を全て見ていた。古くからの女友達のようになった彼女に、会えば癒されていた。
「え、俺は“剛田大”なの?チョコは?」
『“剛田剛” 。剛、だからね』
俺らから電話がかかってきた際。
誰かに画面を見られても大丈夫なように「剛田+名前の一文字」で電話帳登録していると笑った彼女に、俺も笑った。
「チョコ、ジャイアンかよ!笑
つーか、そもそも何で剛田姓なんだよ。」
うけるっしょ、と笑いながら俺の肩に一瞬もたれた彼女に、身体が熱くなった。
絶対に惚れないはずだった。
俺には愛する人がいて、彼女にも彼氏がいたから。
彼女の彼氏が倫さんの親友だと聞いたときは、謎に背筋が伸びて気合が入った。
出会ってから3年後の夏、彼女が彼氏と別れたと聞いた時から、俺の中で何かが変わった。