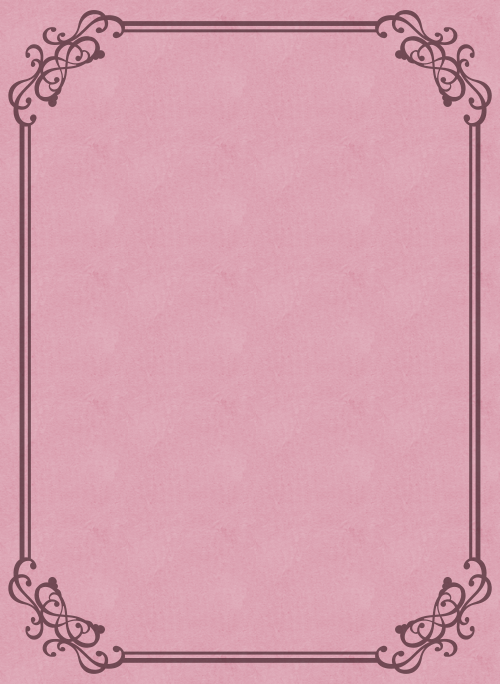バタンーーー
玄関のドアが閉まる音がしてからどれくらい経っただろうか。
水晶はきっと、もう、奏の腕の中にいるだろう。
それとも、暴力を振るわれてるかもしれない。
如月は一人になった部屋の中で、ぼうっとただそれだけを考えていた。
私が男だったら。
何度そう考えたかわからない。
「みーちゃん…」
水晶のいない部屋で名前をつぶやくと、決まって涙が溢れてくる。
私は何もできない。
水晶を救えない。
私はこんなにも水晶が好きでたまらないのに、水晶の一番は私じゃない。
水晶は私を愛してくれているけれど、水晶にとってそれは少し深い関係の親友でしかない。
奏は危険だよ、やめたほうがいい。
何度忠告したかわからない。
水晶は奏が暴力を振らなかったときに戻ると信じて疑わない。
水晶は自分が奏の機嫌を悪くするのがいけないと言う。
愛ゆえの暴力なんて存在しないと何度言っても、水晶には聞こえないのだ。
私にはつらすぎて耐えられないから、逃げるためにこうして泣き続ける。
感情を外に出さないと、自分まで壊れてしまいそうだから。
ピンポーン
誰と確認もせず、インターホンを無視して布団に突っ伏した。
少しして二回目の呼び鈴がなる。
無視を続けると、鍵が開く音がした。
「きーちゃん、いないの?」
やっぱり海斗だ。
「あ、寝てるのか」
部屋に入って、呑気な声でそう言う。
「帰って」
私は涙声を隠すように、小さい声で短く言った。
「起きてたの?」
海斗は明るい声で言って私のそばに座った。