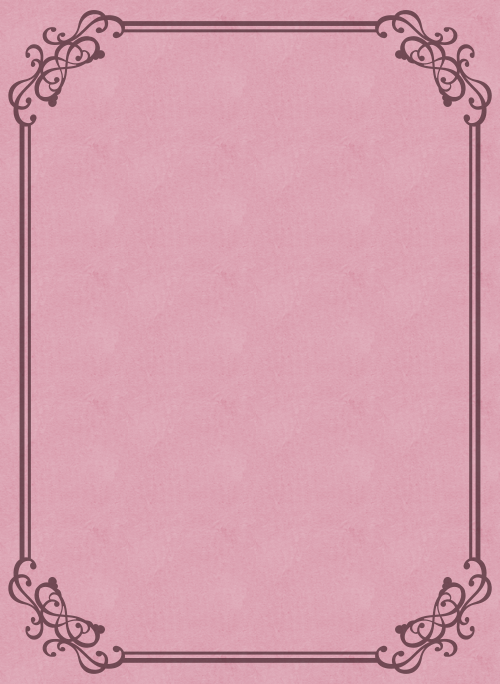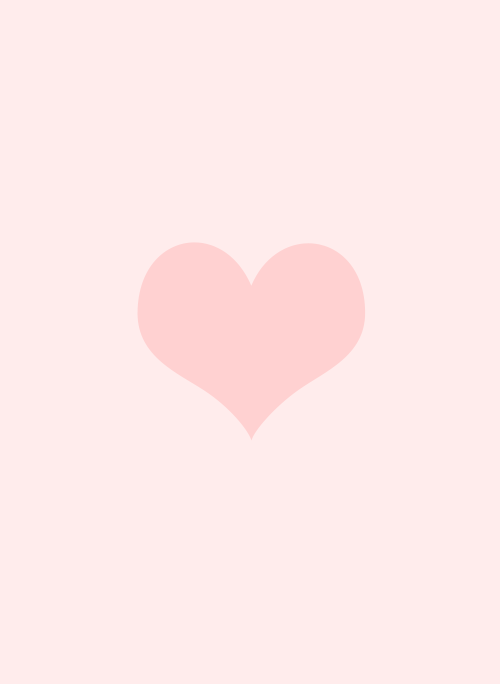「みーちゃん…行かないで…」
私はキスをしながら、涙声で水晶に訴える。
私にとって誰よりも大切な水晶が、わけのわからない男に暴行を受けるのは苦痛でしかない。
私は水晶と一緒にベッドの上に移って、向かい合わせに座った。
水晶の服を脱がせて、下着だけにすると、白い肌に無数にある青あざを包み込むように抱きしめて、たくさんのキスを落とした。
水晶はそんな私を優しく抱いて、頭を撫でる。
「らぎ、あたしね、らぎのことを一番愛してるのよ、でもそれじゃあダメなの」
「私が男に生まれてればよかった」
「それでもダメ、らぎがらぎだったからあたしは安心して愛せたんだよ」
水晶は奏のせいで男性恐怖症になってしまった。
それでも奏から離れられないのは、もう病気なのだ。
水晶と奏を離れさせるためには、奏を逮捕するしかない。
それなのに、当の被害者が被害を認めないのだから、もう第三者には手の施しようがない。
「みーちゃん、私、一度でいいからみーちゃんの中でイキたい」
私は自分が男だったら、水晶を誰よりも幸せにする自信がある。
「それは無理でしょ」
水晶にあっさり否定されて、私は水晶の首筋に顔をうずめた。
「それくらい好きなの…」
言いながらまた水晶にキスをする。
「知ってる」
水晶はキスに答えながら、私の腰に手を回した。
「どうしてもあの男のところに帰らなくちゃいけないの?」
私は泣きそうになるのをこらえながら、水晶に聞く。
「帰るんじゃないの、あたしが帰る場所は奏じゃなくてらぎのところだよ」
水晶は大真面目にそう答えて、私を強く抱きしめた。
先ほどまでキスばかりしていたのに、今度は水晶がキスをするのを静かに待った。
水晶の美しい髪を触りながら、この時間が終わらないことを祈った。
「みーちゃん」
「らぎ」
「愛してる」
「あたしもよ」