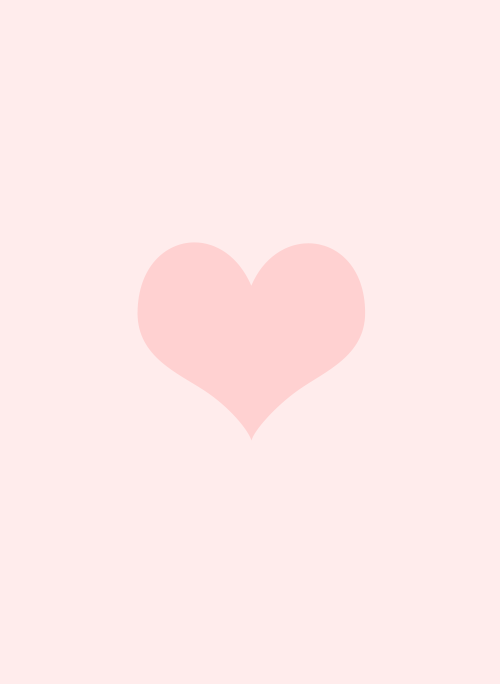布団の中に湯たんぽを入れて、毛布を掛けながら、美晴のおでこに手を当てた葵。
思わず目を見開いた葵は、すぐ様俺を見た。
「一気に上がってるよな〜」
「うん、ビックリした……みぃ大丈夫かな……」
「一応、明日になっても下がらなかったら病院かな……」
「そっか……明日に下がってればいいけど……」
葵の切ない表情は、美晴の熱が長引く事を危惧しているのが分かった。
夜中には、俺たちの心配をよそに、美晴の熱は上がるところまで上がった。
「ハァ……ハァ…ケホケホッ」
暫くして、寒がっていた美晴は、暑がり始め、俺と葵は、美晴の体を冷やし始めた。
脇の下や足の付け根に保冷剤を当てて、体を冷やしている。
「あ、おい……」
「ん?どうした?」
美晴の小さな声を拾ってくれる葵。
「………ごめ、んね」
「どうして謝るの……」
葵は眉を下げている。
「め、わく……」
こんな状態でも美晴は自分を優先しない……
「迷惑なんかじゃないよ。俺が側に居たいからしてるだけ。みぃは、今は治す事だけ考えて? じゃないと、またお出かけできないよ?」
「………うん……て、にぎって」
美晴は葵に向かって、腕をゆっくり伸ばした。
思わず目を見開いた葵は、すぐ様俺を見た。
「一気に上がってるよな〜」
「うん、ビックリした……みぃ大丈夫かな……」
「一応、明日になっても下がらなかったら病院かな……」
「そっか……明日に下がってればいいけど……」
葵の切ない表情は、美晴の熱が長引く事を危惧しているのが分かった。
夜中には、俺たちの心配をよそに、美晴の熱は上がるところまで上がった。
「ハァ……ハァ…ケホケホッ」
暫くして、寒がっていた美晴は、暑がり始め、俺と葵は、美晴の体を冷やし始めた。
脇の下や足の付け根に保冷剤を当てて、体を冷やしている。
「あ、おい……」
「ん?どうした?」
美晴の小さな声を拾ってくれる葵。
「………ごめ、んね」
「どうして謝るの……」
葵は眉を下げている。
「め、わく……」
こんな状態でも美晴は自分を優先しない……
「迷惑なんかじゃないよ。俺が側に居たいからしてるだけ。みぃは、今は治す事だけ考えて? じゃないと、またお出かけできないよ?」
「………うん……て、にぎって」
美晴は葵に向かって、腕をゆっくり伸ばした。