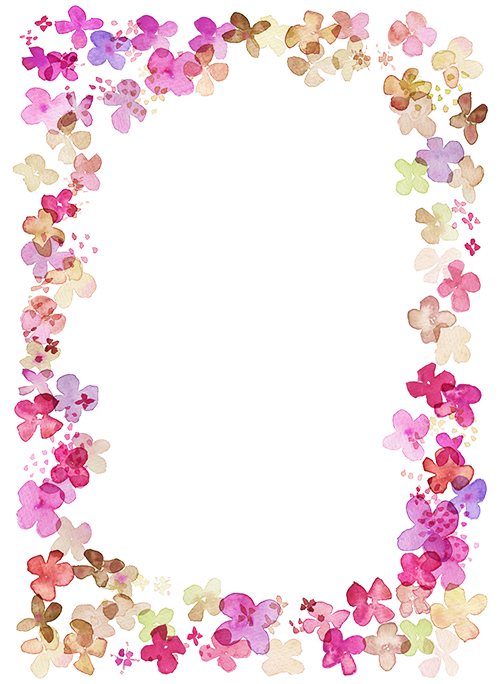お店の奥に行こうとする晴友くんの腕を、わたしは思わずつかんだ。
そんなわたしを見下ろして、晴友くんは驚きと困ったような表情を浮かべる。
「…は。泣きそうな顔してんじゃねぇよ」
だって…
あんまし、ひどいから…。
「どうして…」
「…」
「どうしてそんなにイジワルなの…」
どうしてわたしにだけ、イジワルなの…。
痛っ…。
泣くのをこらえて強張る頬を、晴友くんが軽くつねって、独り言みたいにつぶやいた。
「知らねぇよ…んなこと…。こっちが聞きてぇよ」
…どういう意味…?
思わず見上げると、晴友くんはいっそう不愉快そうに顔を歪めて、突き離すようにわたしから離れた。
「じゃあしっかりやれよ。言っとくけど、もし失敗して店に泥をぬったら、おまえ、クビだから」
テーブルに店員の人たちがファクスで送ってくれた紹介内容の詳細と進行表を置いて、晴友くんはホールに出てしまった。
わたしは途方に暮れて立ち尽くした。
なにがなんだかわからないまま、だったけど、でもひとつだけ確信したことがある。
晴友くんは、やっぱりわたしのことが嫌いなんだ。
大っ嫌いなんだ…。