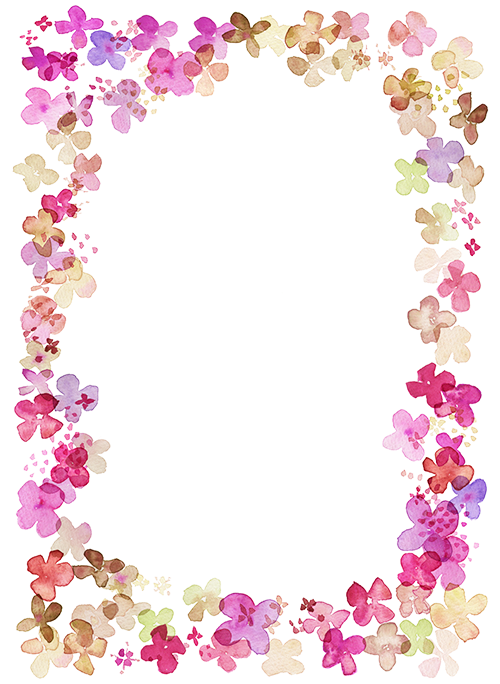「…ああくそ、調子狂う。
おまえ、無自覚でストレートだよな…」
…どういうこと?
首をかしげて見上げると、晴友くんは、
「ほら、そういうとこだよ…」
と、赤い顔で視線をそらした。
「…ったく…おまえといると、ほんと調子狂うよ…。俺をこんなに振り回しやがって…」
フッ、と降参するように溜息をつくと、晴友くんは微笑んだ。
「凌輔さんの言う通り、パティシエとしての実力がない俺は、まだまだおまえには不釣合いだ。
もっともっともっと腕を磨かないと、あの人からは認めてもらえないかもしれない。
でも…
必ずなってみせるよ。凌輔さんを超えるパティシエに。
おまえが見守ってくれるんなら、俺はどこまでだって頑張れる気がするから」
晴友くん…。
「日菜。
おまえは、俺だけのものだからな」
はい…。
とうなづいて、わたしは大好きな彼の胸に頬をすり寄せた。
甘いものが大好きなわたしだけれど、こんなに甘い想いに満たされたのは初めて。
やっと、やっと叶った。
わたしの初めての、大切な、大きな片想い。
今、同じように想いを持ってくれている晴友くんに満たされて、
さすがのわたしも、もうお腹いっぱいで、とろけてしまいそう…。
それでも。
それでもわたしは、望んでしまう。
大好きな、わたしだけのパティシエさま。
これから先も、ご注文は甘い甘い恋を……。
「晴友くん…」
「ん…」
「大好き…」
言葉の代わりに落ちてきたくちづけは、
またわたしを、甘いしあわせにとろけさせてくれた。
Fin