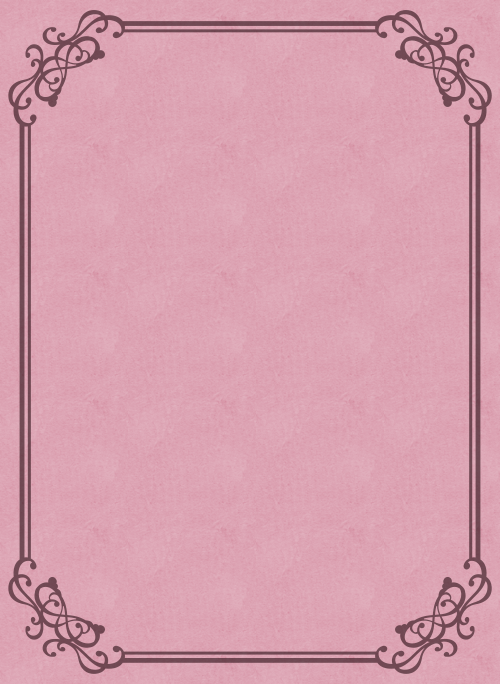………はっ?
「……なぜ、なぜ彼女が!?」
私はおばさまにつかみかかった。
本気ではない。
私の方が背も低いし、おばさまが本当に苦しいのならあっさり降りきれる程度の力だ。
彼女に、アニーに特別な思い入れがあると言うわけではない。
ただのメイドだ。
ただのメイドでただのお世話係。
だが、それでも、
なぜ私の回りのものは、こうも立て続けに
何人も死ななくてはならない?
「アニーはここへ用事があったようなのよ。
そのときに殺されて。」
私は手を離す。
「用事?」
おばさまの方をみた。
するとおばさまは、残念そうに首をふった。
「分からないわ。
当の本人は亡くなっているから。
死人に口無しよ。」
「そう、ですか。」
「ええ。こんなときに、ごめんなさいね。
シャロン…。」
おばさまが私の肩を叩いた。
しかし、同情も慰めも、今の私には必要ない。
いや、ほしくなかった。されると惨めだ。
私はおばさまの手をはねのけた。
「亡くなったものは、
もう戻ってきません。
こんなことでくよくよしている気も、
私はない。」
私は心を落ち着け、深呼吸をした。
そして、
「おばさま、私が留守の間
この屋敷を管理してくださったこと、
当主として、心からお礼申し上げます。」
軽く私は会釈すると、そのまま後ろを
向いて書斎から出ようとドアを開けた。