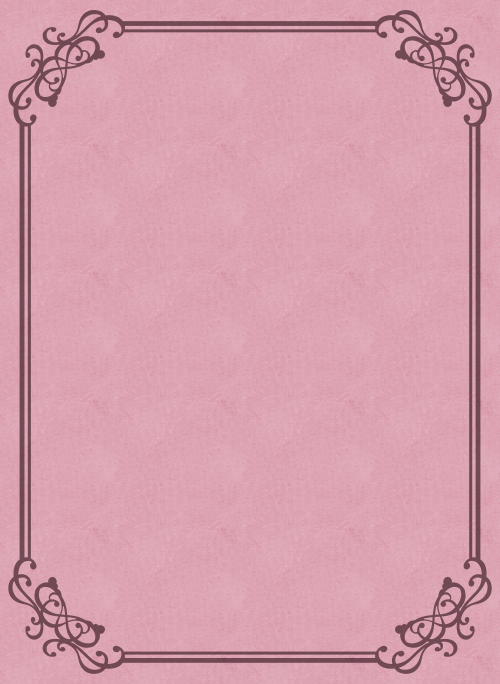時間などあっという間に、ベイリーは予定通りきっちりとやってきた。
どこまでも目につく派手な着飾りで、彼の高慢さは見て取れた。
彼の大きな鼻は敏感すぎてすでに壊れてしまっているのだろう、彼が登場してまだ数mのところで凄まじい香水の香りがした。
いや、香りなどという生易しいものではない。きつい汚臭だ。
あちらはあまりお風呂に入らないと聞くが、香水のふりかける量が半端じゃないから実質フランス人もどきは香水のシャワーを浴びているようなものだ。
「お会い出来て光栄ですよ、ミス・フォスター…いや、この場ではフォスター社長というべきか」
「なんとでもどうぞMr.ベイリー。私もあえて光栄ですわ。
まずはご挨拶として、こちらささやかな贈り物を」
私はそういい、シリウスに合図を送ると、彼は蓋のあいた小箱をベイリーの前へ持っていった。
「おやこれは…」
「当社の人気商品、蜂蜜のナッツ菓子です」
ベイリーの性格は知っている。
相手をおだて、まるで自分は気配り上手で愉快な男と言う風貌を演じながらも、自己顕示欲丸出しなナルシストだ。
そういうやつには早々に餌でもやっとくのが一番だ。
「はっはっは、確かにありがたい手土産。
フォスター社は昔からいろんな分野に手を出されていますからな、うちのような雑貨店ではプレゼントも辛気臭くなってしまいますわい」
そう言って、彼はうやうやしくそれを受け取る。
フォスター社の落ち行く様を肴にしているくせに、よくもまあ言えたものだ。
結局は自分の会社が一番であることを私に言わせ、実感したいだけだろう。
「そんなご謙遜を。最盛期のフォスター社も、雑貨店としてはベイリー社のフランスブランドにはさすがに勝てないでしょう」
「はっはっは、うちは庶民にも慣れ親しんだ会社、まあ、双方とも長所短所あるということで」
彼の会社は根っからのフランスかぶれで、アンシャンレジームが存在していた頃からこんな調子だ。
かくいう我社は、お父様だったか先々代だったか、そのあたりから会社が活発になっていったようだった。
フランスファッションだとか、そういった流行に手を出したのはつい最近で、フランスかぶれの年季が彼らとは段違いなのだ。
私はその後、ベイリーと何気ない雑談をしながら昼食をとった。
驚いたことに、彼は食事中にもかかわらず、ペチャクチャペチャクチャとくだらない話を続けていた。
フランス人は食卓の席では会話を弾ませるという。
別にベイリーがいつから本物のフランス人になったのかという興味はないが、郷に入っては郷に従え、イギリス式にゆっくり味を楽しむことはできないのだろうか。