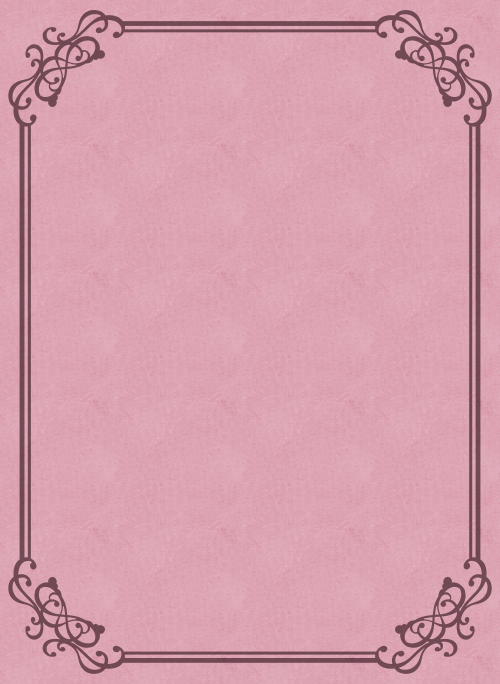まあ恐らく、可愛いアーノルドさえ居ればあの子を撫でるのに20分など短く感じるのだろう。
私はアーノルドと離れてまだ半日ほどしか経っていないというのに、無意識にあの子の無邪気な顔を求めていた。
アーノルド、お前が居なくて私は寂しさを紛らわせる方法すら思い浮かばない…。
しばらくしてからハッと正気に戻った私は時計を見るのだが、針はとても進んだとは言えない位置にいた。
こうも退屈続きでは(私が毎回退屈する性格でもあるが)体が滅入ってしまう。
ふと、また何度目かの思いつきで、机の引き出しを開けた。
オルゴールの箱は、私を呼び寄せるかのように目を惹く出で立ちだ。
開けなければ…と強迫観念に駆られ、オルゴールをパカりと開ける。
「失礼致します」
先程から随分と出入りが激しい。
やれやれ、と思い、しかし暇な時間を潰せるかもしれないと期待しながら私はドアに向かって「入れ」と命じた。
コツコツと革靴が鳴っている。
どうも聞きなれない。顔を上げると、新しい靴を履いたシリウスだった。
「また性懲りもなく宝石を眺めていらっしゃるのですか」
「これほど美しいのに着飾る場所もないというのは哀れだと思いましたので」
「それならば、今から身につけてみては?」
そう言いと、シリウスは私の横からスルスルとブラッド・ジェムを引っ張り出した。
そして、私の後ろ髪を丁寧に払い、その宝石を私の胸元に垂らし、後ろで止めた。
「なにをされる、ベイリーがやつらと手を組んでいるとは思わないですが、見せびらかすものでもないでしょう」
そういいつつも、私は不思議とそれを外したいとは思わなかった。
見れば見るほど、感じれば感じるほど私の体にしっかりと重なっている。
宝石が私を求めているのだと直感的にそう思った。
「ああ、お嬢様、お嬢様、あなたはおわかりになっていない。ブラッドジェムは本来、その麗しい姿を身に着けてこそのものなのです。あなたのような方に」
「少し前まで汚らわしい人間に盗まれたことを嘆いていたのに随分な変わりようだこと」
首から下げた宝石を少し掲げて見つめる。
お父様の言っていた魅せられるとはこういうことだろうか、以前までの底しれぬ恐怖とは反対に、安らかなものを感じる。
まるで、ずっと昔から知っていたような…
「青い宝石を目に宿し、赤い悪魔の石を胸に収める、悪魔との契約をしているあなたには、神聖なものと言えましょう。
そろそろ時間ですし、ええ、ここはゲン担ぎに」
そう言われ、私は時計を見た。
約束の時間の数分前だった。
先程まで遅くて数えるのも面倒だった秒針が、今はとても早く思える。
私はシリウスに「これを守れなかったら私の首が飛びます、しっかりネックレスと私を守ってくださいよ」と念を押した。