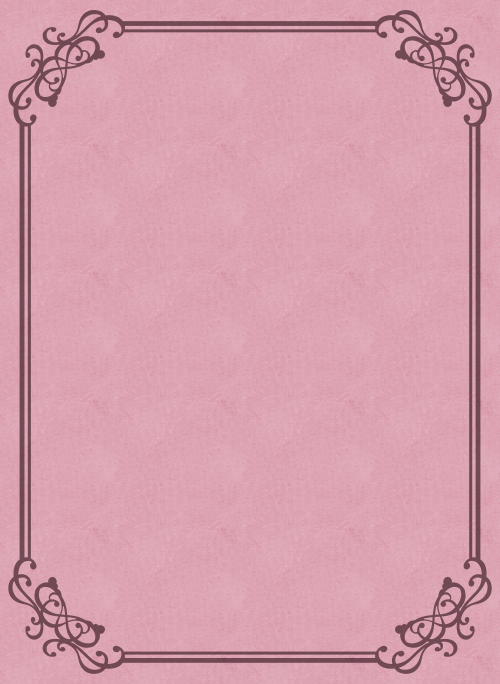一瞬で空気が凍ったのを感じた。
ヴィル爺の細い切れ目が突き刺すようにこちらを見ていた。
あの目は、殺る気だ。今のうちに言い訳でも考えておいた方がいいかもしれない
「はっはっは、愉快愉快、その頑固さ、オリヴァーを思い出す。あなたのしたいようになさりなさい」
こちらの状況も知らずにA.Dはしゃべり続ける。上機嫌なのか、先程よりも随分と声が大きかった。
ヴィル爺の前では肯定もできず、私はただ相槌を打ちながら笑っているしかない。
「その頑固さを持ってしても、旦那様が己の血を絶えさせるなどするはずもございませんが」
紅茶のおかわりを入れる時間がこれほどまでに恐怖を感じた日は今までにない。
ヴィル爺の私を見る目が本当に恐ろしかった。
武闘に愛された男ならではの目なのだろう。
まあ、私としては、武闘よりも微笑みの女神に愛された方がいいように思えるが。
「ウォレストンがご一緒だったとは…なんとも、罰が悪いですな」
ヴィル爺の声に気づいたのだろう。
A.Dは慌てて「しかし、血を途絶えさせるかどうかを決める必要は何も今すぐでなくても良いでしょう?」と付け足した。
ヴィル爺の事を慮ってそういったのだろう。やはり声は少し大きかった。
ヴィル爺もそれを聞き、上機嫌のように見える。
「あぁ、少し長話をしてしまいましたね、シャリ。何度も言うようですが、あなたにお会い出来るのを楽しみにしております」
「ええ、私もです。是非とも。
アンナにも会いたいですし、それに、A.Dと父との話を聞かせていただきたいです」
「ええ、もちろん。それではさようなら」
A.Dはにこやかにそう言い、電話を切った。
ヴィル爺は未だになぜか部屋にいる。
私は入れられた紅茶を飲んだ。
そこまで時間は経っていないはずだが、少しぬるかった。
きっと、ヴィル爺の凍りつ様な目にお茶も冷めたのだろう。
「あなたに、何か考えがあって、もしくは何か忌まわしい記憶があって拒んでいるのであれば、爺は何も申しません」
「忌まわしい記憶?」
少し考え込んでから、私は答えを出した。
すなわち、彼は私を心配しているのだ。
伯爵家の令嬢を誘拐した男から何もされていないとは言いきれないのだろう。
(実際には殺されかけた直後にシリウスが例の場所へ転送したのだが、それだと都合が悪いので他の物には誘拐されたあと上手く抜け出せたことになっている)