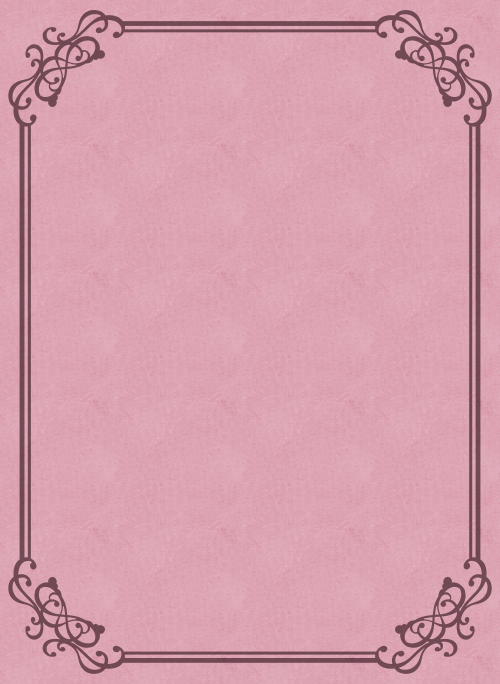受話器を置く音が聞こえる。
私はA.Dを待つ間、何を話そうか考えていた。
アンナを挟んで話しをすることはあっても、ADと2人で話すことなど、記憶を辿ったが二、三程しかない。
アンナの様子を聞くのが大前提ではあるが、向こうも私の様子を知りたいだろう。
「お電話変わりました」
受話器を持ち上げる音がした後、細く低い、しゃがれた老人の声が聞こえた。
彼の声は私の知っている自信に満ち溢れた、それでいて厳しい声色のA.Dの声とは打って変わって、病気の老犬が主人を探すかのような弱々しい声だった。
「お久しぶりです、A.D」
「シャリ、お久しぶりです。
前までの可愛らしい娘の声と変わり、レディの声ですね。お母様によく似ている」
昔を懐かしむかのような彼の声に、私はどこか侘しさを感じた。
レディレディと毎日のように言われた忌まわしい言葉さえも、この瞬間ばかりは成長出来たのだろうかと少しだけだが嬉しくなった。
「母のようにはまだまだなれませんが、ええ、時間は流れました。私も少しだけ、変わったのだと思います」
「そうですね、私もすっかり歳をとりました。時の流れはよくわかっています。
それ故に、オリヴァー…いえ、お父様とお母様の件は、とても、とても残念でした。」
A.Dは少し、間を置いて呼吸をした。
そしてポツポツとか細い声で1音1音区切りながら、言葉を確かめてるのように話し始めた。
「彼は、良き友であり、兄弟のような存在であり、時には、年齢は若くも、私の父のような存在でした。きっと、ナンシーもこの事実を知ったら、同じ思いとなるはずです」
「あなた方夫婦に慕われた父と母は、幸せな方々でした」
「シャリ、あなただけでも生きていてよかったと、どれほど涙を流したことか」
その後、暫くはお父様とお母様の話が延々と続いていた。
昔話とまでは行かないが、2人がどんな人物だったか、私がその時何をして、アンナは何を思っていたか、など、A.Dとの会話は、しばらく忘れていた記憶を呼び起こさせた。
「しかし、あの可愛らしくも憎たらしい妖精のようなシャリが、今では女伯爵とは」
「ええ、少し前の私なら、自分がこうなるとは思っていませんでした。
良い顔をする人間には未だ巡り会えていませんし、賛同するとしても悪魔か、よほどの_____女性の権利を主張しているもの達ぐらいしか賛同しないでしょうね」
「ええ、いかにも。私とて、それに賛同することはできません、しかし、フォスターの血が途絶える訳では無いのなら、それでいいのかもしれませんな」
「どの道、残念ながら私の代で途絶えるのでしょうがね」
と私が話した時、ガサリとドアの向こうで音がした。
それからノックがなるので、私は入るのを許可する為に机を1度だけ叩く。
シリウスだろうか。
時間的に、まだベイリーがくる訳はないので、きっと紅茶の継ぎ足しかなにかだろう。
「あなたで途絶えさせるのは行けませんな、この老いぼれグレゴリー男爵の血と違い、あなたはまだまだ血筋を残せる」
何度も聞いた小言だ、私は流す。
ちょうどノブが回され、開かれた扉から尖った靴が私の部屋へと入った。
「いえ、私はもう、そんな気力がないのです。とはいえ、私の中では途絶えさせてしまうのは確定していますが、ヴィル爺の前だと口が裂けようが言えませんね」
この瞬間、私はこの男を中へ入れたことを後悔した。
そこに居たのはヴィル爺だったのだ。