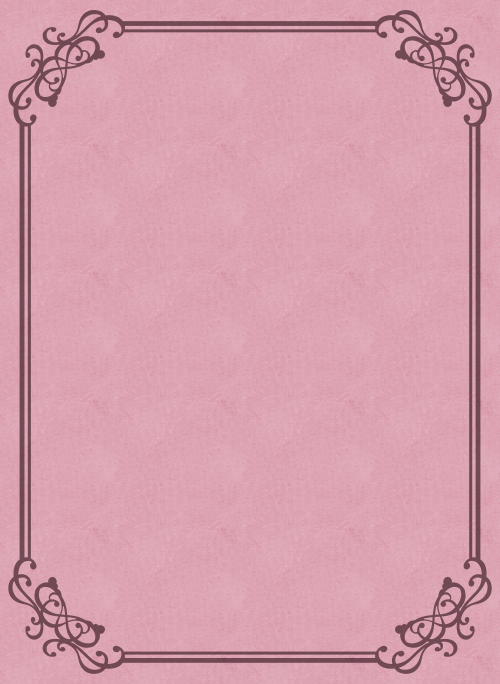しかしそれをしたとして、それは私ではなくお父様なので、次に私は自分ならどうするか考えてみた。
そうだ、シャロン・フォスターという人間は、こう言うときにどうするだろう。
今の私はまるで過去の“お嬢様”に戻ってしまっているようだ。
使用人に結婚相手の話を延々と聞かされ、それから逃げるかのように書斎に閉じ籠る。
いったいどちらが主人なのかわからない。
私らしい私が描く
シャロン・フォスターなる女性は、
父親の思慮深さ、冷静さ、冷血さ、
母親の即決力、勇気を受け継いでいる。
では、そんな私が今すべき事はなんだろうか?
答えは、なにもしない、だ。
自分でも不思議なくらい直感的に、これが正解に思えた。
ヴィル爺に何か言っても、彼は言葉が次から次へと出てくる。
まるで飼い主にあらかじめ何を言うか覚えさせられたインコのように、たんたんと。
普段は私が彼を珍しくも誉めようが、
誉めたときよりも少ないが感謝の意を表そうが、なにもしゃべらないか無表情だというのに。
もしかすると私に注意をするときだけ舌が生えて出ているんじゃないかと思う。
そう思っていると、なにやらドアを引っ掻く音が聞こえた。それと鳴き声。
私は迷わずドアを開け、アーノルドを迎え入れた。
「アーノルド、お前は怪我をしていないかい?」
まあ恐らく、シリウス達が取り逃がしたのが私が殺した男一人だけならば、
アーノルドは無事なはずだ。
しかし、一応確認してみた。
まず、アーノルドに伏せをさせ、医者にでもなった気分であちこち撫でたり見てみたりした。
何をされているのかわかっていない
アーノルドは、首を傾げて鼻を鳴らす。
「大丈夫そうだな」
元気そうなアーノルドを見て私はフッと笑い(こんなときですらうまく笑えていない自分に嫌気がさす)、
横においてある本棚から本を取り出した。
自分の好きな本も置いていたが、お父様の持っていた本が殆どだった。
遺留品を燃やすとは言ったものの、
二人の所有物はなにかと役立つ物が多い。
二人の服、小物、家族との思い出らしき写真など、その辺は燃やし捨てさせたが、それ以外の貴重品は全て保管した。
私が今読んでいる本は、医学の本だ。
あちこちに書き込んであったり、新聞の記事が挟まれていたりする。
これを読む限り、お父様はこれから設立される病院に投資するつもりだったようだ。