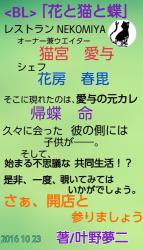次の日 夕方
僕は結月さんたちの家におじゃますることになった。
陽裕さんは、家に帰ることを嫌がるかもしれないからと結月さんが提案してくれた。
「もうすぐで着くって」
不安だらけで、ちゃんと伝えられるか、心配だった。
「そんなに心配してんじゃねぇ。
思ってること、全部言えばいい」
澪さんは、僕の頭を撫でてくれた。
そうして、陽裕さんが入ってきた。
「依利……、何でここに?」
「じゃあ、僕たち出掛けてくるから、二人でちゃんと話すんだよ」
「えっ、ちょっと」
珍しく陽裕さんは、取り乱していた。
「今日、俺ら、ホテルに泊まるから、ここに泊まっても良いぞ。
嫌なら、オートロックだからそのまま帰っていい」
「でも」
「じゃあ、行ってくるから」
そう言って、二人は出掛けていった。
「はぁ、全くあの二人は……」
なんて、話せば良いんだろう?
四日間も話してないとなに話せばいいか分からないや。
「依利、ソファ、座ろっか」
「はい」
隣同士に座った。
それでも、陽裕さんは、僕の目を見てはくれなかった。
でも、結月さんも澪さんも思ってること話せばいいって言ってた――。
「陽裕さんは、僕のこと嫌いですか?」
「えっ、そんなわけないだろ」
そっぽを向きながら、答えた。
「目もあわせてくれないんですね。
やっぱり、嫌いですよね」
「だから、それは――」
「それでも、良いから、側に居させて下さい」
陽裕さんの声を遮るような少し大きい声が出た。
「嫌いなら、疎ましいなら、不愉快なら、
僕を叩いて下さい、蹴って下さい、殴って下さい。
それでも、側に居られるなら僕は幸せですから……、それに、痣や傷はその人が僕に触れてくれた証です。
陽裕さんが触れてくれるなら、どんな形でも嬉しいです。
だから、こんな僕を側に置いてくれませんか?」
「本当に言ってるの?」
やっと、こっちを向いて話してくれた。
「はい、陽裕さんが好きです。
だから、側に居たい。
陽裕さんになら、何されても良いです。」
自然と笑顔で話せていた。
陽裕さんが目をあわせてくれるだけでこんな嬉しくなる。
そっと、陽裕さんが抱き締めてきた。
「陽裕さん?」
「俺は、依利が居ないと楽しくない」
「ごめんなさい」
「やっと、分かった。
依利は、もっと俺に愛されてる自信を持て
俺がもっともっと愛してやる」
陽裕さんが、愛してくれる。
「陽裕さん、僕のこと、好きですか?」
「依利だから、好きだ」
「陽裕さん、僕も大好きです」
僕は結月さんたちの家におじゃますることになった。
陽裕さんは、家に帰ることを嫌がるかもしれないからと結月さんが提案してくれた。
「もうすぐで着くって」
不安だらけで、ちゃんと伝えられるか、心配だった。
「そんなに心配してんじゃねぇ。
思ってること、全部言えばいい」
澪さんは、僕の頭を撫でてくれた。
そうして、陽裕さんが入ってきた。
「依利……、何でここに?」
「じゃあ、僕たち出掛けてくるから、二人でちゃんと話すんだよ」
「えっ、ちょっと」
珍しく陽裕さんは、取り乱していた。
「今日、俺ら、ホテルに泊まるから、ここに泊まっても良いぞ。
嫌なら、オートロックだからそのまま帰っていい」
「でも」
「じゃあ、行ってくるから」
そう言って、二人は出掛けていった。
「はぁ、全くあの二人は……」
なんて、話せば良いんだろう?
四日間も話してないとなに話せばいいか分からないや。
「依利、ソファ、座ろっか」
「はい」
隣同士に座った。
それでも、陽裕さんは、僕の目を見てはくれなかった。
でも、結月さんも澪さんも思ってること話せばいいって言ってた――。
「陽裕さんは、僕のこと嫌いですか?」
「えっ、そんなわけないだろ」
そっぽを向きながら、答えた。
「目もあわせてくれないんですね。
やっぱり、嫌いですよね」
「だから、それは――」
「それでも、良いから、側に居させて下さい」
陽裕さんの声を遮るような少し大きい声が出た。
「嫌いなら、疎ましいなら、不愉快なら、
僕を叩いて下さい、蹴って下さい、殴って下さい。
それでも、側に居られるなら僕は幸せですから……、それに、痣や傷はその人が僕に触れてくれた証です。
陽裕さんが触れてくれるなら、どんな形でも嬉しいです。
だから、こんな僕を側に置いてくれませんか?」
「本当に言ってるの?」
やっと、こっちを向いて話してくれた。
「はい、陽裕さんが好きです。
だから、側に居たい。
陽裕さんになら、何されても良いです。」
自然と笑顔で話せていた。
陽裕さんが目をあわせてくれるだけでこんな嬉しくなる。
そっと、陽裕さんが抱き締めてきた。
「陽裕さん?」
「俺は、依利が居ないと楽しくない」
「ごめんなさい」
「やっと、分かった。
依利は、もっと俺に愛されてる自信を持て
俺がもっともっと愛してやる」
陽裕さんが、愛してくれる。
「陽裕さん、僕のこと、好きですか?」
「依利だから、好きだ」
「陽裕さん、僕も大好きです」