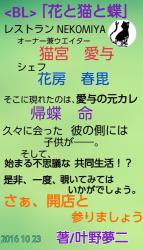次の日
もう、限界だった。
父の苛立ちも、身体のアザも
増えていく一方で――。
もう、一人で抱えきれない。
痛くて、辛くて、悲しかった。
ピンポーン
その音だけが静かな家に響いた。
痛む身体を労りながら、玄関へと足を動かした。
やっとのことで、玄関を開いた。
「あっ、依利君、こんにちは」
優しく微笑みかけられた
この笑顔は、僕に向けられているんだ。
倒れこむように竜崎さんに抱きついた。
「えっ、依利君、どうしたの?」
「タ…テ、オネ…」
「今なんて言ったの?」
「たす、けて、おね、がい」
竜崎さんの背中に回した手は震えていた。
「良くできました。
その言葉を待ってたよ」
また、あの優しい手で頭を撫でられた。
もう、限界だった。
父の苛立ちも、身体のアザも
増えていく一方で――。
もう、一人で抱えきれない。
痛くて、辛くて、悲しかった。
ピンポーン
その音だけが静かな家に響いた。
痛む身体を労りながら、玄関へと足を動かした。
やっとのことで、玄関を開いた。
「あっ、依利君、こんにちは」
優しく微笑みかけられた
この笑顔は、僕に向けられているんだ。
倒れこむように竜崎さんに抱きついた。
「えっ、依利君、どうしたの?」
「タ…テ、オネ…」
「今なんて言ったの?」
「たす、けて、おね、がい」
竜崎さんの背中に回した手は震えていた。
「良くできました。
その言葉を待ってたよ」
また、あの優しい手で頭を撫でられた。