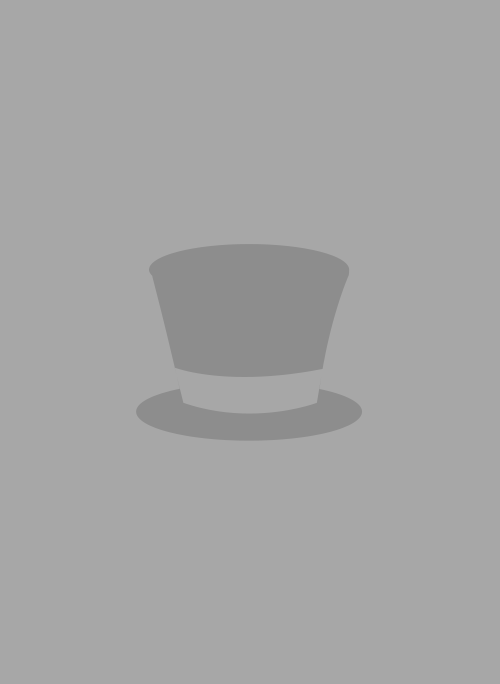『おとうさん、おれさ、きょう……』
『わるいまこと、ゆうとがないてるから、あとにしてくれ』
『……わかった』
成海は記憶の道を進んでいく。
『お父さん、おれ、先生にほめられたんだよ』
『そうか。それより、そこのたなからゆうとのオモチャ、とってくれないか』
『……うん』
成海の足音は止まらない。
『まことくん、さいきん元気ないね。なにかあったの?』
『……なんにもないです』
『そう……なんでも言ってね』
成海の顔立ちは、母譲りだった。
やや吊りあがった目と、細い眉。成海が父に似ていたのは、強い癖のある髪のみだった。
『こら、ゆうと、ちゃんとご飯を食べなさい』
『あ、こぼれた!もう、ゆうとったら……』
『……ごちそうさま。ぼく、部屋にいるから』
4分の1の弟の髪も、成海と同じように癖っ毛だった。しかし弟の目は穏やかな丸い形をしていて、父と再婚相手の女性の遺伝をバランス良く受け継いでいた。
『……父さん、バスケの練習手伝ってよ。小学校でバスケやってるやつ、誰もいないんだ』
『今は無理だ。明日やろうか』
『昨日もそう言って……わかった。1人でやってくる』
道の左右に転がるバスケットボール。
『諒くん、勉強できてる?数学と理科くらいならあたしでも教えられると思うんだけど……』
『……英語以外ならできるんで、大丈夫です』
『そうなの?諒くんすごいね。でも、英語はあたしも教えられないかな……ごめんね』
2度目の母。本当の母親とは、似ても似つかぬ穏やかな顔立ちをした女性だった。
『諒兄ちゃん。バスケ教えて!』
『僕より父さんの方が上手いから、父さんに教えてもらえば?僕は……教えるの、下手だし』
『えー……じゃあ、いいや』
家の中で、成海についてくる義理の弟。
『父さん、明日のバスケの試合で、僕がスタメンに選ばれたから、暇なら……』
『そうか、よかったじゃないか。そういえば、明日は祐斗の参観日なんだよ』
『……へぇ』
父の心から、抜け落ちた自分。
中学1年の夏。
放課後の部活が終わり、バッシュを持ち、1人であかね道を歩いていた成海は、道の先に見覚えのある女性が立っているのを見た。
景色が歪む。