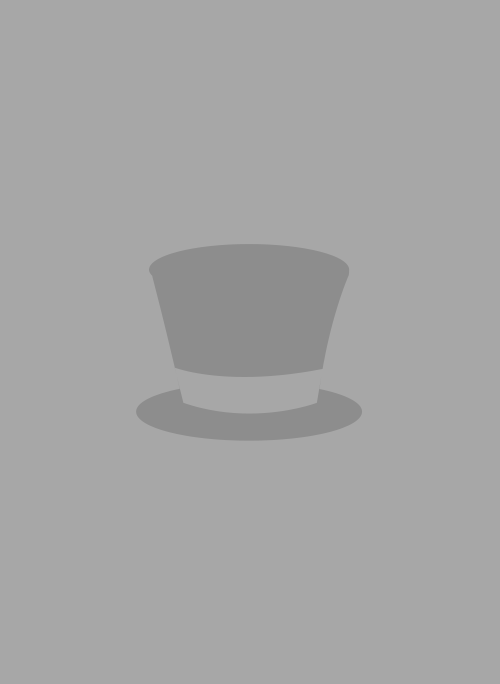真夏のかげろうのように風景が揺らぐ。
成海自身を除いて。
汚れひとつない天井、床、壁。白によって乖離された空間。成海は病院の廊下に設置されたベンチに、たった1人で座っていた。
背を向けた部屋の中から、大人たちの騒がしい声が絶え間なく耳に届いてくる。
『成海さん!もう少しだ、力を抜いて!』
『がんばれ、あともう少しの辛抱だ、ほら、ずっと手を握っているから』
あれから6ヶ月後の深夜2時、7歳の成海のまぶたは重くなっていった。彼はベンチに横になり、そっと目を閉じる。
『ほら、あと少しだ!がんばれ、……!』
『成海さん呼吸を意識して!もうすぐっ……』
一瞬の静寂、そして病院の静けさを打ち消すような赤子の泣き声が響き渡った。
反射的に、成海は息を止める。
『生まれた!俺と……の、初めての子供だ!』
父がはしゃぐ声。血の繋がりのない母が、息も絶え絶えに泣きながら言った。
『この子は……大切に、してあげなくちゃ』
膝を抱え、くの字に折り曲げた背中と、固いベンチ。無機質な白い壁と同化するように、成海は眠りに吸い込まれていった。