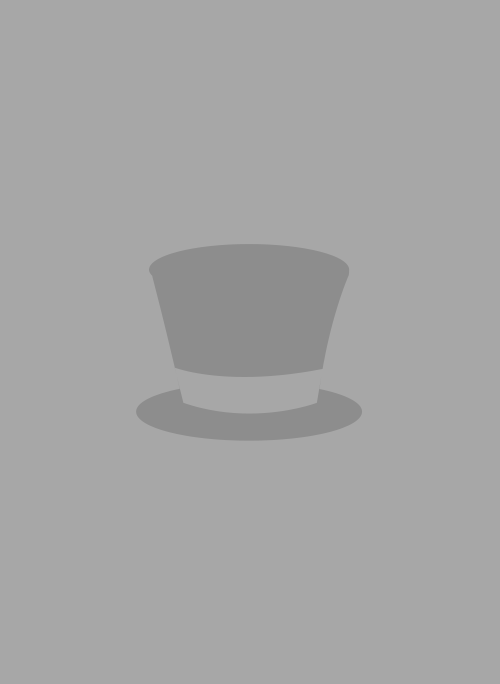走馬灯の中を走り、半年後の風景が夢に浮かび上がる。
玄関の戸口に立ち、成海のことを興味深く観察するように見つめる女性がいた。
『このこがおれのむすこだよ。まことっていうんだ』
父の手が成海の背中に添えられる。
『へぇー……すごくかわいいのね。あなたそっくりだわ』
『そうか?ははおやにだとよくいわれるが』
『こんにちは、まことくん』
女性はにこやかに腰を曲げ、成海に桃色のマニキュアを塗った右手を伸ばす。
『あたしは、……っていうの。これからいっしょにすむことになるけど、ほんとうのおかあさんだとおもってくれていいからね』
成海は微動だにせず、ぼんやりと彼女の手を眺めた。
彼女は手を引っ込め、気まずそうに笑う。
『やっぱりいきなりはむりだよねえ……』
玄関には、冷気が漂っていた。外は雪が降っていたらしく、彼女のセミロングの髪には白い結晶がいくつも乗っていた。
『ちゃんとあいさつしなさい』
父が肩を軽く叩く。
『……こんにちは。おれ……』
『まこと、おしえただろう。あいさつのときは、“おれ”じゃなくて“ぼく”だ』
『……ぼくは、なるみ まこと、です』
女性は満足げに成海に微笑みを向け、再び成海の前に手を差し伸べた。
『ちょっとずつ、なかよくしていこうね』
成海は女性の手を握り、視線を移した。
コートをまとう彼女の腹は、心なしか膨らんでいるように見えた。