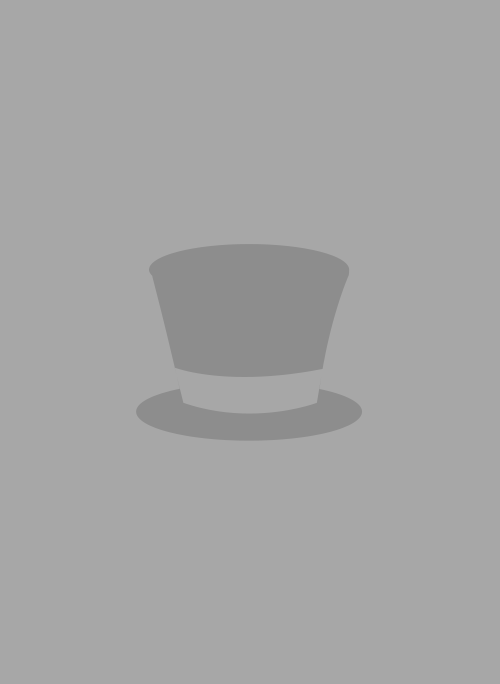目を開けた成海は、自分が今、夢を見ていることを知った。見下ろした両手が普段よりふたまわりほども小さく、華奢な形をしていたからだ。低い目線で見る世界には、懐かしさを覚える。
これは、彼が6歳だった頃の記憶の断片。
頭を撫でる、白いしなやかな手。自分に目線を合わせてしゃがむ女性。
『……ごめんね、まこと。こうするしかなかったの。こうするしか……』
薄く霧のかかった顔で彼女は微笑み、両手で成海の頬を包み込む。温かい体温が、直に伝わる。
『……そんなかおしなくてもだいじょうぶ。おとうさんをしんじて、ね?』
動かない、幼い自分の影。
『はなれていても、まことはわたしのこどもだからね。わすれないから』
『……いやだ、おれ、ずっとおかあさんといっしょがいい』
頬から手を離し、笑顔を消した母。彼女は無言で立ち上がり、後ろずさった。長い黒髪をなびかせて、彼女は向きを変えて歩いていく。
『やだ、いやだ、おかあさん!』
追いかけようとした成海の腕を、大きい手が掴んだ。
『まこと、やめなさい。おかあさんは……まことからはなれていたほうがいいんだよ』
『……なん、っで……おれ……おかあ、さん』
濡れていく視界。薄らいでいく母の影。
大粒の涙が滴る。
それは蒸し暑い、雨の日のこと。