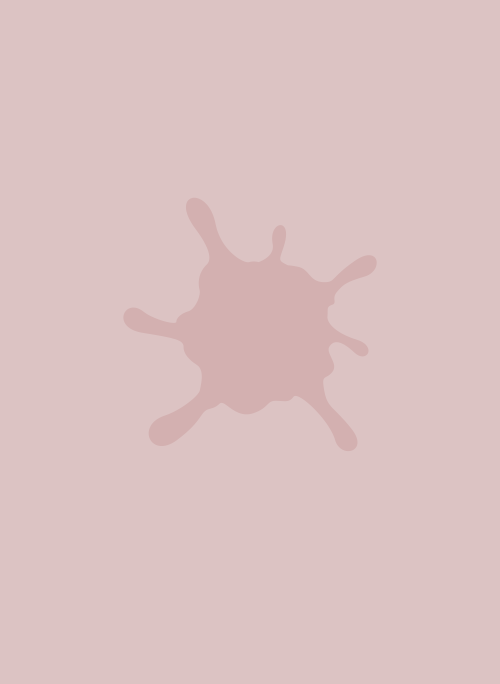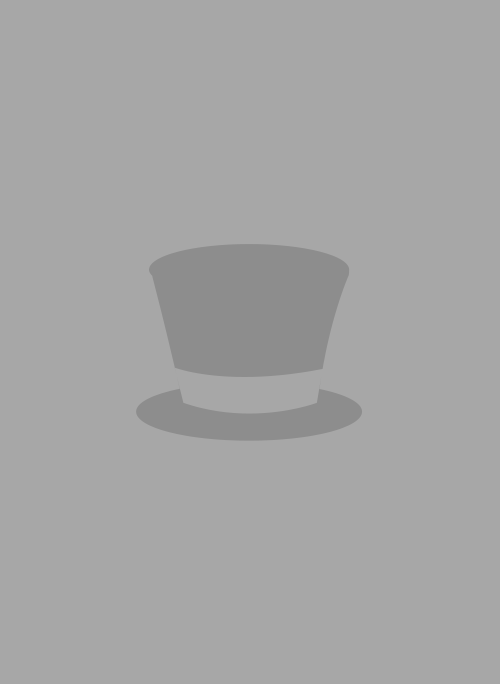「クラムボンは、あたしなんだよ?」
後方の窓に成海の体を押さえつけ、カッターナイフを喉に突きつけたまま詩織は言った。赤い血が切っ先に滲み、成海は顔を歪める。
周は息を呑み、身を屈めた。
手のひらを汗が湿らせる。体験したことのない緊迫感に、心臓が激しく脈を打つ。
扉を隔てた数センチメートル先は、現実から大きく外れた異空間だった。
「……そんなことを言うために、僕を呼び出したのか?」
怒りを押し殺しているような、いつになく低い成海の声が聞こえる。
「そう。……殺されたくないなら、あたしと付き合ってよ。あたしは、全部、知ってるから。6月30日に成海が猫を殺したことも」
沈黙が流れ、周は胸を押さえる。
「……っ!」
がっと鈍い音が響いた。
瞬間的に体がわななき、息を殺す。周は緩やかな動作で体を起こし、見つからないよう扉の小窓を覗いた。少しでも気を抜けば体が扉にあたり、物音を立ててしまいそうになった。
教室に音はない。
「……ふざけるなよ」
成海の背中が見えた。
窓に押しつけられた詩織は、怯えながらも恍惚とした表情を浮かべていた。カッターナイフを右手に構え、成海は彼女の首に刃を当てる。
成海の顔は周の場所からは見えない。
何が起こったのかを理解するには、数秒の時間を要した。
鳥肌が立つ。
校舎にこもった熱が周の呼気にまとわりつく。
赤いカッターナイフが教室の隅で際立っている。銀色の刃がまぶしい。忘れられたコンパスが、教卓の前の机に置かれていた。
白百合が活けられた花瓶は、浜田の机の上に金剛石の粉をはいたような影を形作っている。
成海はカッターナイフを微かに震わせ、
言葉をつないだ。
「クラムボンは、僕だ」
夏を殺したクラムボン
–––END