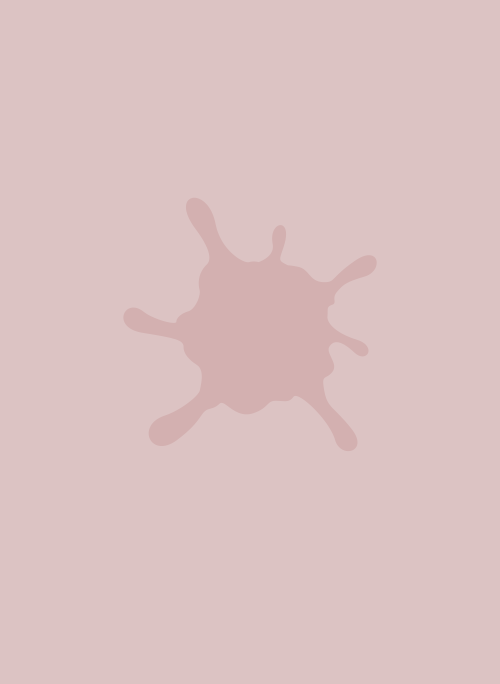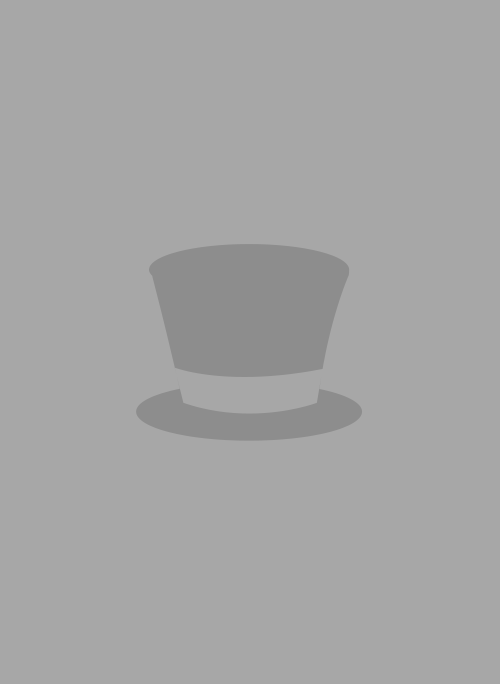K中学校近くの交番の前で周はリュックの肩掛けを強く握りしめた。炎天に焼かれ、彼女の額に幾筋もの汗が伝う。
ポケットの中に入れている詩織のカッターナイフは、まるで岩石を運んでいるかのように重かった。
教室に残してきた成海のことを思い起こし、周は静かに目をつぶり、頰の肉を噛む。
……成海がなぜ、誰のためにあんなことをしたのかはわからない。でも、もしも私と成海がもっと早くに話をしていたら、どうなっていただろう。
私はどうして、
成海のことが気になったのだろう。
自転車に乗った中年の女性が怪訝な顔で周の背後を通っていった。
交番を前にすると足が竦む。これから重く長い夏休みが来るのかと思うと、例えようのない暗澹たる気分に押しつぶされそうになった。
目の奥から滲んだ何かが視界を曇らせ、やがて汗にまぎれて頰に流れ落ちる。
……これは、なんの涙?
手の甲で1度拭うと、もう涙は出なかった。
交番の扉を開けた瞬間、涼しい風が吹いた。中には青い制服に身を包んだ2人の警官が居座っており、周を見ると眉をひそめて互いに顔を見合わせた。
汗が冷える。少し、肌寒い。
「どうしましたか?」
優しそうな顔つきの中年警官は穏やかに周に尋ねた。途端に言おうとしていた言葉が喉の奥でつまり、息ができなくなる。
……私と成海は、よく似ていた。
それは唐突な思考だった。
……あの感情は、
きっと不覚の同族意識だった。
その感情を、
私ひとりだけが勝手に抱いていた。
周は口を開く。
「M市中学生殺人事件の犯人は、
K中学校、2年4組の……成海 諒です」
警官2人の驚いた顔を眺めながら、昨日の放課後のことを想起する。
……クラムボンと、カッターナイフ。