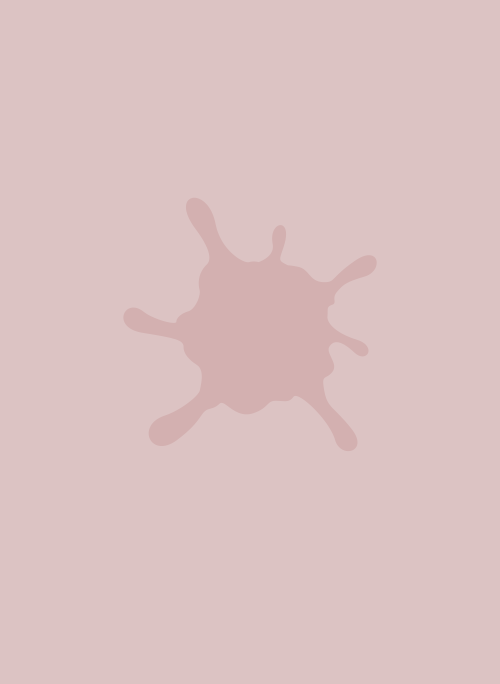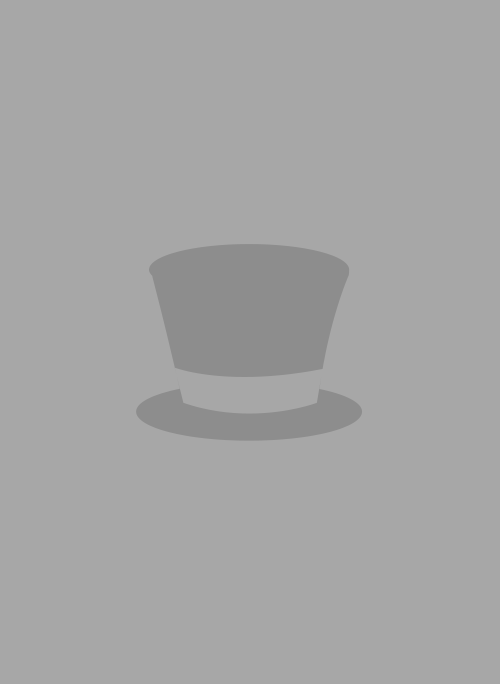中学1年の夏だった。
7月の初旬、放課後の部活が終わり、成海はバッシュのケースを手に、ひとりであかね道を歩いていた。体操服は汗に濡れ、夕陽が雲を赤く染めて、長い影法師がコンクリートの道に伸びる。
交差点で赤になったばかりの信号に歩みを止め、成海はふと自分を生んだ母親の顔を想像した。
……僕の母さんは、どんな顔だったか。
吊りあがり気味の目と、多分色白で、髪は真っ直ぐな黒髪。父さん曰く、僕と母さんは生き写し、だったらしいけれど。
具体的なイメージが思い浮かばず、成海はため息をつき、顔を上げる。
「……え?」
世界から音が消え、成海は目を疑った。
100メートルほど先の道端に、見覚えのある女性が立っていた。彼女の顔立ちは、毎朝鏡で見る成海そのものだった。
長い黒髪が涼やかな夏風に揺られている。車道にとまった赤いポルシェと、赤く発光する信号機の残像。
バッシュと学校指定のリュックを投げ捨て、成海は一目散に走り出した。
赤信号は制止の意味を成さず、息が荒れ、ただひたすらに全力で一本の道を駆ける。
くらりと視界がぶれ、成海は夏の空気を裂いた。
それは、直感でしかなかった。
騒がしい夏の午後、交差点の信号が一斉に色を変え、景色が流れ、両目の奥に焦げるような熱を感じた。
あと、20メートル。
心音が、高鳴る――。
瞬間、疾走する成海を赤いポルシェが追い抜き、長い黒髪の女性の前でブレーキをかけた。
反射的に成海は足を止める。
残り、10メートルほどの距離。