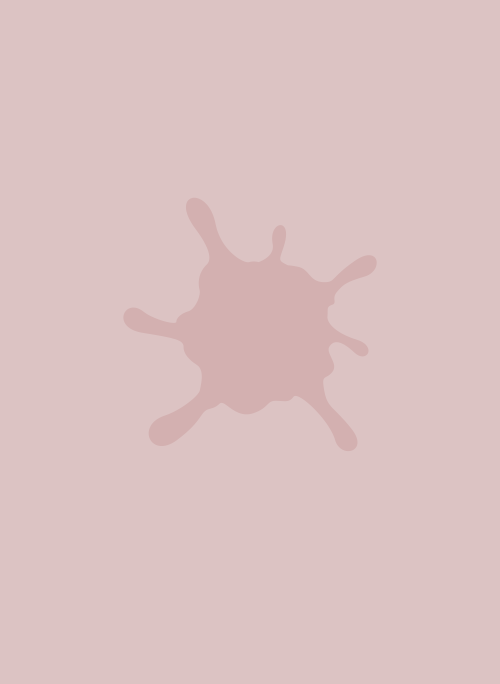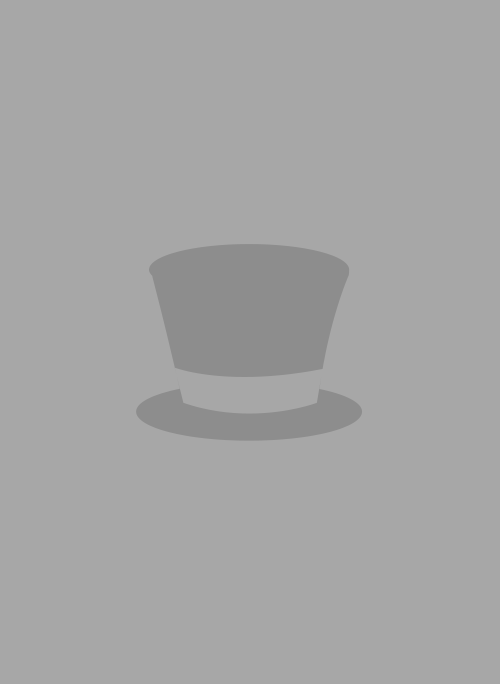「約束って、なんだ?」
「……え?あれは、成海が……」
「もしかして、力になるって言ったこと?」
「そう、だけど……」
成海は無表情で周を見つめ、天井を仰ぐ。ぬめりとした冷ややかな雰囲気が2人きりの教室に蔓延し、周の肌に執拗にまとわりついた。
「……ねぇ、葉月」
窓際の最前列の机上に腰を乗せ、成海は呆然と扉の前に立ち続ける周に問いかける。
「葉月は今でも死にたいと思ってるのか?」
「……死にたいって?」
言い淀む周を、成海は静かに見ている。さんさんと降り注ぐ日光が、成海の背中を熱する。
徐々に上がっていく室内の気温。
手のひらが汗で滑る。
「……死にたくない」
周は小さく声を絞り出した。
「あの日は、死にたいと思ってた。でも、成海が、私のせいじゃないって言ってくれたから……」
「……はは。なにそれ」
……死にたくないというなら、先に約束を破ったのは、葉月だ。
成海は笑い、ため息をついた。
「僕は葉月が死にたいって思っていたから、“力になる”って言ったんだよ」
「え……?」
「本当は誰だってよかったんだ。
罪悪感なんて、元からなかったから」
唯一下の名前を呼ぶ、浜田の声が聞こえる。
『あれ、諒。なにしてんの、ここで』
浜田の頚動脈をナイフで掻っ切った瞬間の感覚が全身を巡る。
夜道、偶然を装って塾帰りの浜田に話しかけ、警戒心のない顔を見ながら、ひと気のない、誰ひとり来ない空き地へと足を進めたこと。多量の鮮血が顔や服にかかったが、成海は気にしなかった。
人体の切断は思っていたよりも力が必要だったため、いつの間にか時刻は真夜中になっていた。
ばらばらになった浜田を残し、成海はキッチンの包丁立てに立てられていたナイフを持ったまま、家路につく。暗い帰り道に人の気配はなく、父や義理の母、弟は寝たのか、家に明かりはついていなかった。
血まみれのナイフを軽く洗い、返り血を浴びた服を可燃ごみの袋に入れ、家の前に放置する。袋は翌日の朝、ゴミ収集車により回収される。
“M市中学生ばらばら殺人”として大々的にニュースに取り上げられた事件は、誰も、成海の犯行だということに気づかなかった。
成海の思惑に反して。
周の体が微かに震えている。
「罪悪感がないの?」
「ないよ。だって、僕はただ……」
ふと成海は言葉を切ると、潰れた白百合に目を落とし、唇を噛んだ。ひとときの静寂が流れ、周の額に汗が伝う。
「僕が……僕が悪いなんてことは
何一つないんだから、
僕が気にする必要もないだろう?」