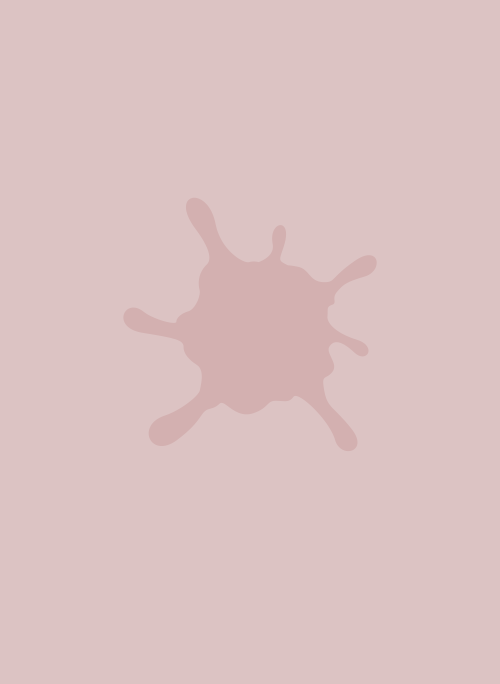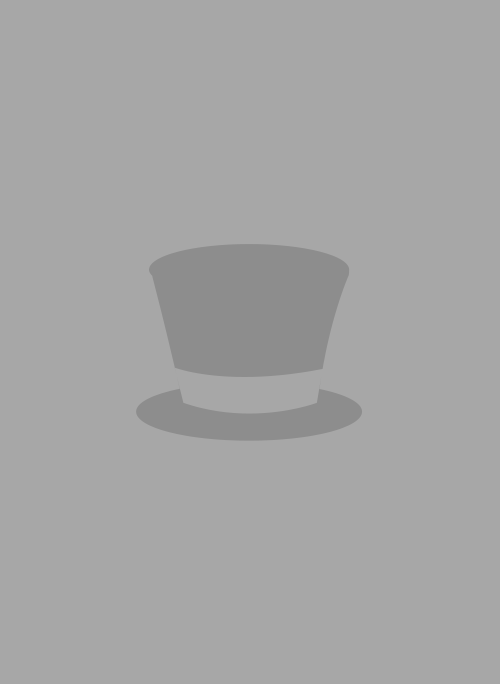手に持った白百合がやけに熱く感じられた。手のひらを夏の陽光で焼かれるような感覚がし、成海は花を床に投げ捨てる。
「気づいたのはいつ?昨日か、もっと前か。靴箱に紙を置いてたんだから、朝の時点で気づいていたんだろう?」
周は唇を震わせ、成海から目を逸らす。
彼は薄笑いを絶やすことなく白百合の花を上靴の底で踏みにじる。
「……違和感が、あったの。浜田が殺されたときから、ずっと、少しだけ」
扉にもたれかかり、周は成海の問いに答えた。
「……例えば、成海は……私が小動物を殺した犯人って言ったとき、すぐに『犬を殺した犯人』だって言い換えた。その時はなんとも思わなかったけど、なんでか、引っかかってた」
「あぁ。一応は気になっていたのか」
成海が足を浮かせると、消しゴムの屑のような薄汚れた白百合の花弁が床にこびりついていた。純白の花弁に含まれていた水分が、木の床にいびつな円形を描いている。
「もともと成海は、浜田や小動物を殺した犯人にあまり興味を持っていなかったのに、葬儀の日、犬や猫を殺したのは窪田だって、すぐに突き止めたことも、違和感があった」
「浜田と小動物を殺した犯人を、僕はすでに知っていたから」
「……他にも、猫の死骸が机の中に入れられていたとき、あんなに怒っていたことも。あのときは、あの日の約束を守ってくれたのかと思った。でも……」
「約束?」
ふっと、成海が笑みを消す。