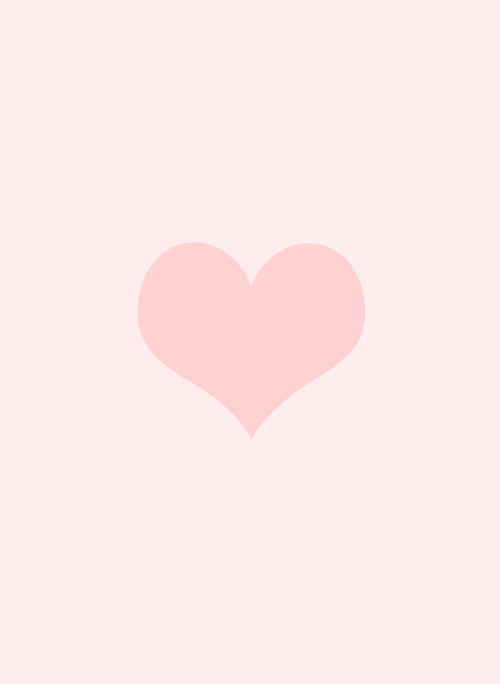「オレのことはいいんだよっ!華月だよ、本当に脈アリだと思うか?」
勢いのまま立ち上がり、ウロウロと部屋を歩き回りながら詩月の返事を待つ。「んー?」ともったいつけながら詩月が続ける。
「恋愛に関心のなかったはーちゃんが、たっくんがやらしく迫った結果、あんなにオロオロしてるんだよ?たっくんに脈があるかどうかはわかんないけど、ちょっと異性にドキドキする気持ちは知っちゃったよね。ふふふー。」
楽しそうに笑う詩月の言葉の不本意な部分に気付いて、「おい、待て」と足の動きを止めた。が、続きを言う前に詩月が再び口を開く。
「あ、それでね。たっくんのチョコなんだけど、保留中なのね。イヤなら私が作るって言ったんだけど。だから、当日まで待て。夜中まで待て。」
「…お、おう。」
相変わらず詩月は楽しそうに笑っている。
そりゃそうだろう。恋愛無関心の妹が変わっていく様を見ているのも、幼馴染みが恋愛成就できるかどうか高みの見物するのも、純粋に楽しいよな。自分のことじゃないし。
そんなことより、そうか、華月、ちょっと揺さぶられたか…。
よしよし。
頬が緩むのを止められず、誰も見ていないのに口元を手で覆う。
束の間の沈黙の後、詩月が信じられないことを言った。
オレは黙ってそれを聞く。
「…ま、そういうことだから。あ、はーちゃんお風呂あがったみたい!じゃ、おやすみっ!」
「しづ…」
おやすみと返す間もなく機械音が繰り返される。
全く慌ただしい。
再び頬が緩んで口角が上がる。
明日もやらしく迫ってやろうじゃねぇか。