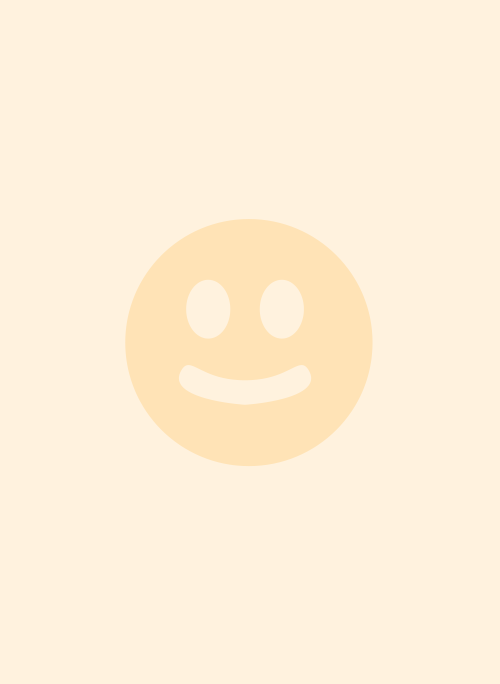それに、何故だか無性にむしゃくしゃして、思わず責めるような口調になってしまう。
「考えてみたことがあるか?冬の間の、桜の気持ちを」
そいつはしばらくうーん、と考えて、
「あるよ」
とだけ答えた。
考えたことがあるくせに、そんなふうに言えるのか。
「花を咲かせている間は、人々は自分を愛してくれる。だから幸せなんだ。だけど、いざそれら全てが散ってしまうと、もう人々は自分の存在すら忘れてしまう。愛される幸せを知った花は、また、春になり花を咲かせる。そして散る。人々は、また、自分を忘れる。いったいそれのどこが、健気と言える?」
それはもう、なかば八つ当たりだった。
僕の言葉を、ただ静かに聞いていた朝日奈 悠は、閉じていた瞼をゆっくりと開く。
「だからこそ、桜は健気なんだよ」
「考えてみたことがあるか?冬の間の、桜の気持ちを」
そいつはしばらくうーん、と考えて、
「あるよ」
とだけ答えた。
考えたことがあるくせに、そんなふうに言えるのか。
「花を咲かせている間は、人々は自分を愛してくれる。だから幸せなんだ。だけど、いざそれら全てが散ってしまうと、もう人々は自分の存在すら忘れてしまう。愛される幸せを知った花は、また、春になり花を咲かせる。そして散る。人々は、また、自分を忘れる。いったいそれのどこが、健気と言える?」
それはもう、なかば八つ当たりだった。
僕の言葉を、ただ静かに聞いていた朝日奈 悠は、閉じていた瞼をゆっくりと開く。
「だからこそ、桜は健気なんだよ」